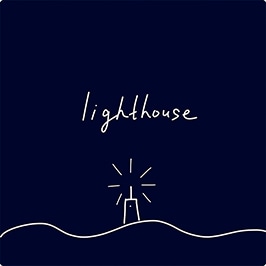こちらのウェブストアは運営停止しています。
購入は新ストア(以下のボタンをクリック)よりお願いします。
*Tシャツなどのグッズはこちらで購入可能です。
-

西瓜になった父(+こだま薬袋)
¥200
SOLD OUT
2023年11月11日開催の文学フリマ東京にて初売りとなったこだまさんのエッセイです。 父が死に際に遺したふたつの言葉、賑やかな葬式 湿っぽくならなかった我が家の今年の夏の出来事をありのまま書きました A6(文庫)サイズ・12p 絶妙に入らない薬袋つきでお送りします。 *本当はちゃんと入るサイズのつもりだったのですが、まさかの「内側糊付けタイプ」だったため入りませんでした。そういう運命。なお、ちょっと無理すると入るので試したい人はどうぞ。ジョンソンベビーオイルの使用はお控えください。
-

こだまさんZINE「寝ないと病気になる」
¥500
SOLD OUT
こだまさんと担当編集高石さんの協力のもと、非常にしょうもなければろくなこともないZINEが誕生しました。 祝・初版500部、2刷500部、3刷300部、計1300部完売。4刷300部、重版出来です(2023年10月20日)。意味わからん。 (2018年9月初版刊行)
-

超個人的時間旅行
¥1,650
SOLD OUT
タイムトラベル同人誌 「超個人的時間旅行」 上田誠、古賀及子、こだま、スズキナオ、せきしろ、堀静香、宮田珠己、宮崎智之、牟田都子、ワクサカソウヘイ、藤岡みなみ 装画:Ayumi Takahashi 主題歌:ロースケイ「タイムラインでつかまえて」 「現実世界でのタイムトラベル」をテーマにエッセイを書いていただいたアンソロジーです。SF的な主題ですがすべてノンフィクション。タイムトラベルの実用書でもあります。
-

[再入荷待ち]鬱の本
¥1,980
SOLD OUT
本が読めないときに。 鬱のときに読んだ本。憂鬱になると思い出す本。まるで鬱のような本。 「鬱」と「本」をめぐるエッセイ集。84人の鬱の本のかたち。 (夏葉社さまの『冬の本』にインスパイアされてつくった作品です)。 この本は、「毎日を憂鬱に生きている人に寄り添いたい」という気持ちからつくりました。どこからめくってもよくて、一編が1000文字程度、さらにテーマが「鬱」ならば、読んでいる数分の間だけでも、ほんのちょっと心が落ち着く本になるのではいかと思いました。 病気のうつに限らず、日常にある憂鬱、思春期の頃の鬱屈など、様々な「鬱」のかたちを84名の方に取り上げてもらっています。 「鬱」と「本」をくっつけたのは、本の力を信じているからです。1冊の本として『鬱の本』を楽しんでいただくとともに、無数にある「鬱の本」を知るきっかけになれば、生きることが少し楽になるかもしれないという思いがあります。 この本が、あなたにとっての小さなお守りになれば、こんなにうれしいことはありません。あなたの生活がうまくいきますように。 目次 「鬱」ベースの社会に (青木真兵) 怪談という窓 (青木海青子) 犬に限らず (安達茉莉子) にぐるまひいて (荒木健太) 世界の色 (飯島誠) 形を持った灯りを撫でる (池田彩乃) 棚からぼたもち落ちてこい (石井あらた) ブランコ (市村柚芽) 憂鬱と幸福 (海猫沢めろん) 世界の最悪さを確認する喜び (大谷崇) 人と共感できず、なにしろもがいていた頃の話 (大塚久生) 椎名誠『僕は眠れない』 (大槻ケンヂ) 高校時代 (大橋裕之) ウツのときでも読める本 (大原扁理) 低迷期の友 (荻原魚雷) 多摩川で石を拾おうとした (落合加依子) ポジティブ。 (柿木将平) 布団からの便り (梶本時代) 『金髪の草原』の「記憶年表」 (頭木弘樹) やらない勇気 (勝山実) 天窓から光 (上篠翔) 生れてくるという鬱 (切通理作) 「できない」自分との向き合い方 (こだま) 深い深い水たまり (小見山転子) 我輩はゴムである (ゴム製のユウヤ) 鬱の本 (佐々木健太郎) 弱々しい朝 (笹田峻彰) 不良作家とAI (佐藤友哉) ある日、中途半端に終わる (左藤玲朗) 本は指差し確認 (篠田里香) ゆううつと私 (柴野琳々子) 中学生日記 (島田潤一郎) 俺は鬱病じゃない (下川リヲ) あの娘は雨女 (菅原海春) 旅 (杉作J太郎) 十九歳と四十七歳の地図 (鈴木太一) 悪意の手記を携えて (第二灯台守) 願い (髙橋麻也) 君も蝶 (髙橋涼馬) 静止した時間の中で (高村友也) Life Goes On (瀧波ユカリ) 鬱時の私の読書 (滝本竜彦) ちいさな救い (タダジュン) いのちの気配 (谷川俊太郎) 喘息と明るい窓 (丹治史彦) 毎日があるまでは (輝輔) とかげ (展翅零) 沈黙のオジオン (トナカイ) 大学をやめたい (鳥羽和久) 西村賢太という比類なき衝撃 (友川カズキ) 空の大きさと愛の切符 (友部正人) たたかれて たたかれて 鍛えられる本と人 (豊田道倫) 神経の尖った人の見る世界 (鳥さんの瞼) かけ算とわり算 (永井祐) 2023年4月 (七野ワビせん) 曖昧なものの博物館 (西崎憲) 戦友 (野口理恵) きこえる声で話してくれた (初谷むい) 言葉の声が案内してくれる (東直子) ゲーテをインストールする。 (Pippo) 脱法ドラッグ米粉 (姫乃たま) 何度もめくる、自分はここにいる (緋山重) 深夜のツタヤ (平野拓也) このバカ助が (pha) NHKにさよなら! (ふぉにまる) 鬱、憂鬱、10代、と言われ放出したレテパシー (古宮大志) 鬱は小説の始まり (増田みず子) ため息を深く深く深く深く……ついてそのまま永眠したい (枡野浩一) 人間の鬱 (町田康) 憂鬱な銀河 (マツ) それがかえって (松下育男) 夕に光 (miku maeda) あなたが起きるまで (みささぎ) ダメになって救われる――町田康のこと (水落利亜) うつのサーフィン (水野しず) 本が読めた日 (無) 蜘蛛と解放区 (森千咲) 俯きながら生きている (森野花菜) 喋らないヒロイン (山崎ナオコーラ) 悲観論者のライフハック (山﨑裕史) たぶん、不真面目なんだと思う (山下賢二) ぼくの精神薬 (屋良朝哉) なにかに抱かれて眠る日がある (湯島はじめ) *点滅社よりお知らせ↓ 2023年11月21日発行の『鬱の本』第一刷に誤りがありました。 ●169ページ 俯きながら生きている 森野花菜 文末の下記の2行が抜けておりました。 「本を読むということは、俯きながらも生きるということ。いつまで歩けばいいのかわからなくなったとき、鞄の中の本はそっと私を立ち止まらせてくれる。」 ------------------------------------------ この2行を自分で書き足すとより大切な1冊/1編になるような気がします。ぜひ。(本屋lighthouse・関口竜平)
-

実験と回復
¥1,600
SOLD OUT
僕のマリ、日記集。 2023年4〜9月の半年間の記録です。 商業出版、自費出版、トークイベント、一週間ごとに発熱する身体……転がるような日々を送りながら、ずっと患っていた心の不調と向き合います。幸せとは、結婚とは、家族とは。自分が嫌だと思っていること、怖いと思うこと、そんな感情の機微を毎日書き続けて、ひとつずつ検分してきました。自分のなかで半ば負担に感じていた、家族という呪いについての答えが、やっとわかってきた気がします。 114ページ収録、装画作品はタカヤママキコさんです。
-

Books(tore) witness you. vol.1
¥900
SOLD OUT
本屋lighthouseの日記ZINEシリーズ、創刊します。 vol.1は2023年3月〜2023年9月の日記を中心に、各種媒体に載せたエッセイや書評などを詰め込みました。 〈あとがきより抜粋〉 お店の売上とマリーンズのことばかり書いていたような気がしましたが、思ったよりもいろいろなことを考えていたようです。当然、考えていたことをすべて書き残せたはずもなく、考えるそばから忘れていくものたちばかり。忘れていったものたちはどこかに集っているのだろうか。集っていたらいいなと思うけど、喧嘩ばかりしている気もする。みんな違うことを言ってるから。 〈目次〉 4 2023年3月〜 16 私はなぜ書くのか 2023/03/11 22 2023年4月〜 42 私たちは常に誰かに救われているし同時に誰かを救っているらしい、ということ 映画『そばかす』感想文 2023/01/25 54 2023年5月〜 72 書評 『埋没した世界 トランスジェンダーふたりの往復書簡』 74 2023年6月〜 92 すべての野蛮人を根絶やしにせよ!(Exterminate all the brutes!) 98 2023年7月〜 110 宿題が終わらない人生について 映画『わたしは最悪。』 2022/08/30 120 2023年8月〜 138 Books(tore) witness you. 144 2023年9月〜 166 書評 『セミコロン かくも控えめであまりにもやっかいな句読点』 ----------------------------------------------- 書誌情報 本文172p A6サイズ(文庫版) 表紙カラー/本文モノクロ 表紙用紙:上質紙135 本文用紙:上質紙70 価格:900円(税込) 著者:関口竜平(本屋lighthouse) 発行所:本屋lighthouse
-
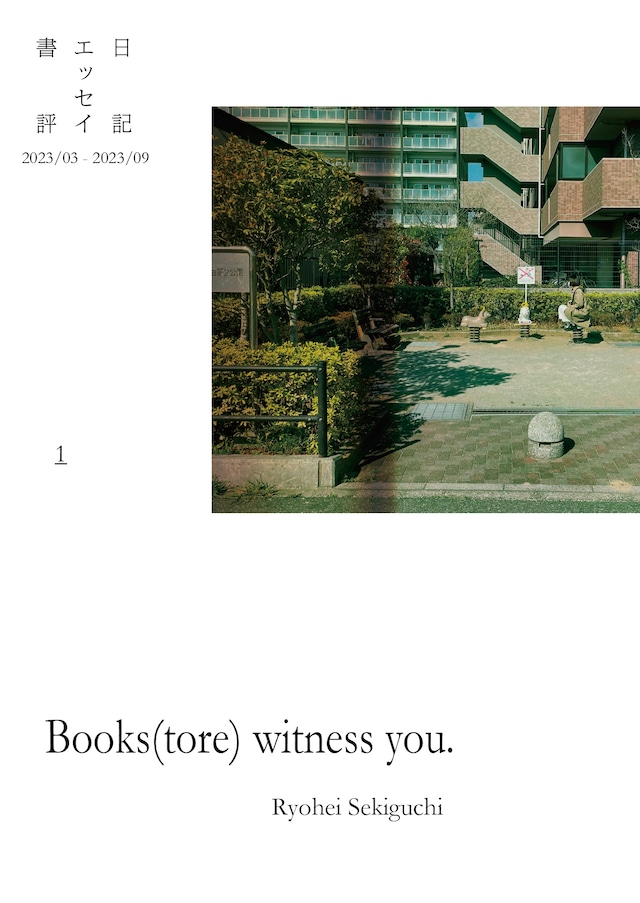
〈電子版〉Books(tore) witness you. vol.1
¥500
SOLD OUT
*こちらは〈電子版〉です。PDFデータ(ALT付)とEPUBデータ(固定型)の2種類がセットになっています。 本屋lighthouseの日記ZINEシリーズ、創刊します。 vol.1は2023年3月〜2023年9月の日記を中心に、各種媒体に載せたエッセイや書評などを詰め込みました。 〈あとがきより抜粋〉 お店の売上とマリーンズのことばかり書いていたような気がしましたが、思ったよりもいろいろなことを考えていたようです。当然、考えていたことをすべて書き残せたはずもなく、考えるそばから忘れていくものたちばかり。忘れていったものたちはどこかに集っているのだろうか。集っていたらいいなと思うけど、喧嘩ばかりしている気もする。みんな違うことを言ってるから。 〈目次〉 4 2023年3月〜 16 私はなぜ書くのか 2023/03/11 22 2023年4月〜 42 私たちは常に誰かに救われているし同時に誰かを救っているらしい、ということ 映画『そばかす』感想文 2023/01/25 54 2023年5月〜 72 書評 『埋没した世界 トランスジェンダーふたりの往復書簡』 74 2023年6月〜 92 すべての野蛮人を根絶やしにせよ!(Exterminate all the brutes!) 98 2023年7月〜 110 宿題が終わらない人生について 映画『わたしは最悪。』 2022/08/30 120 2023年8月〜 138 Books(tore) witness you. 144 2023年9月〜 166 書評 『セミコロン かくも控えめであまりにもやっかいな句読点』 ----------------------------------------------- 書誌情報 本文172p PDFデータ(ALT付) EPUBデータ(固定型) 価格:500円(税込) 著者:関口竜平(本屋lighthouse) 発行所:本屋lighthouse
-

みんなもっと日記を書いて売ったらいいのに
¥1,320
SOLD OUT
84ページ/A5変形・平綴じ/300部 半年間だけ出していた『月刊つくづく』の同名連載にくわえて、あらたに飯田エリカさん、僕のマリさん、星野文月さんとの日記にまつわる対談を収録。 社会が混迷を極めるなかで、個人が日記を書き、売る。その行為の先に何があるのか。わたしの個人的な問いかけに端を発する、小沼理さんの日記にまつわるエッセイ集。巷では日記ブームとも言われていますが、日記って何でしょう。その一端を掴んでいただけたら幸いです。(『つくづく』編集人・金井タオル) --- 著者プロフィール 小沼理(おぬま・おさむ)/ライター・編集者。1992年富山県生まれ、東京都在住。著書に『1日が長いと感じられる日が、時々でもあるといい』(タバブックス)。寄稿に『文學界』(文藝春秋)、『怒りZINE』(gasi editrial / タバブックス)、朝日新聞「ひもとく」など。 --- つくづくポケットライブラリは、細長い判型が好きすぎるあまり、自分でも細長い判型の本をつくりたくて始めたシリーズです。通常は「A5変形」と呼ばれるのでしょうが、個人的には「A4三つ折りサイズ」と言いたい。パンフレットでよく見る、あのサイズ感です。
-

ガザとは何か パレスチナを知るための緊急講義
¥1,540
SOLD OUT
【緊急出版!ガザを知るための「まず、ここから」の一冊】 2023年10月7日、ハマース主導の越境奇襲攻撃に端を発し、イスラエルによるガザ地区への攻撃が激化しました。 長年パレスチナ問題に取り組んできた、 パレスチナ問題と現代アラブ文学を専門とする著者が、 平易な語り口、そして強靭な言葉の力によって さまざまな疑問、その本質を明らかにします。 今起きていることは何か? パレスチナ問題の根本は何なのか? イスラエルはどのようにして作られた国? シオニズムとは? ガザは、どんな地域か? ハマースとは、どのような組織なのか? いま、私たちができることは何なのか? 今を知るための最良の案内でありながら、 「これから私たちが何を学び、何をすべきか」 その足掛かりともなる、 いま、まず手に取りたい一冊です。 ■目次■ ■第1部 ガザとは何か 4つの要点/イスラエルによるジェノサイド/繰り返されるガザへの攻撃/イスラエルの情報戦/ガザとは何か/イスラエルはどう建国されたか/シオニズムの誕生/シオニズムは人気がなかった/なぜパレスチナだったのか/パレスチナの分割案/パレスチナを襲った民族浄化「ナクバ」/イスラエル国内での動き/ガザはどれほど人口過密か/ハマースの誕生/オスロ合意からの7年間/民主的選挙で勝利したハマース/抵抗権の行使としての攻撃/「封鎖」とはどういうことか/ガザで起きていること/生きながらの死/帰還の大行進/ガザで増加する自殺/「国際法を適用してくれるだけでいい」 ■第2部 ガザ、人間の恥としての 今、目の前で起きている/何度も繰り返されてきた/忘却の集積の果てに/不均衡な攻撃/平和的デモへの攻撃/恥知らずの忘却/巨大な実験場/ガザの動物園/世界は何もしない/言葉とヒューマニティ/「憎しみの連鎖」で語ってはいけない/西岸で起きていること/10月7日の攻撃が意味するもの/明らかになってきた事実/問うべきは「イスラエルとは何か」/シオニズムとパレスチナ分割案/イスラエルのアパルトヘイト/人道問題ではなく、政治的問題 ■質疑応答 ガザに対して、今私たちができることは?/無関心な人にはどう働きかければいい?/パレスチナ問題をどう学んでいけばいい?/アメリカはなぜイスラエルを支援し続けるのか?/BDS運動とは何? ■付録 もっと知るためのガイド(書籍、映画・ドキュメンタリー、ニュース・情報サイト) パレスチナ問題 関連年表 本書は、10月20日京都大学、10月23日早稲田大学で開催された緊急セミナーに加筆修正を加えたものです。 著者 岡 真理 1960年生まれ。東京外国語大学大学院修士課程修了。在モロッコ日本国大使館専門調査員、大阪女子大学人文社会学部講師、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を経て、早稲田大学文学学術院教授。専攻は現代アラブ文学・第三世界フェミニズム思想。 Kindle→https://amzn.to/3txaPS4
-
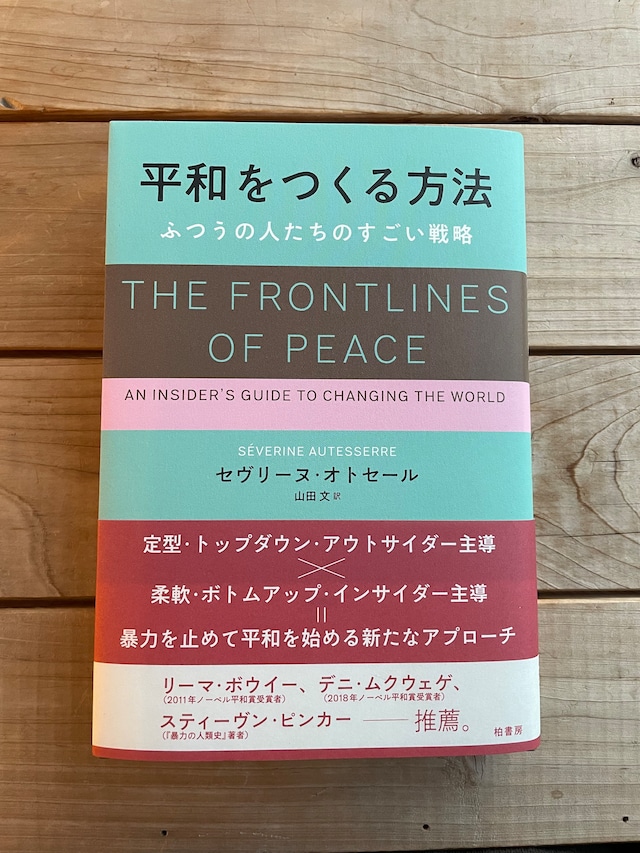
平和をつくる方法 ふつうの人たちのすごい戦略
¥2,860
SOLD OUT
★紛争研究会が選ぶ「2022年ブック・オブ・ザ・イヤー賞」最終候補作 ★寄せられた賛辞の一部 「平和は可能だがむずかしい。…大きなアイデアと現場のファクト、その両方を知る専門家に耳を傾けることが欠かせない。『平和をつくる方法』は人類の最も崇高な試みについて新たな洞察を与えてくれる」──スティーヴン・ピンカー(『暴力の人類史』著者) 「セヴリーヌ・オトセールは、コンゴであれ、コロンビアであれ、アメリカであれ、日々、地域社会で暴力を減らすために努力している普通の女性や男性の物語を語る。読者に行動を促す、魅惑的で感動的な物語だ」──デニ・ムクウェゲ(2018年ノーベル平和賞受賞者) 「『平和をつくる方法』は、ありふれた国際政治の本ではない。まわりの世界の見方を変える一冊だ」──リーマ・ボウイー(2011年ノーベル平和賞受賞者) ★内容 平和構築という言葉は、私たちが何度も耳にした物語を想起させるかもしれない。ある地域で暴力が発生すると、国連が介入し、ドナーが多額の支援を約束し、紛争当事者が協定に署名して、メディアが平和を称える。そして数週間後、ときには数日後に、暴力が燃えあがる──そのような物語。 はたして、私たちに持続可能な平和を築くことなど可能だろうか? 可能だとすればどのように? そうした問いに答えるのが本書である。 著者は、善意にもとづくが本質的な欠陥を抱える「ピース・インク」と彼女が名付けるものについて──その世界に身を浸しながら(参与観察)──考察する。最も望ましくない状況であっても平和は育まれることを証明するために。 そのため、従来とは異なる問いの立て方もする。つまり、〈不思議なのは…紛争解決の取り組みが失敗するのはなぜか、ではない。ときどき大成功を収めるのはなぜか、だ〉。 そう、多くの政治家や専門家が説くのとは反対に、問題に大金を投じても解決策になるとはかぎらない。選挙で平和が築かれるわけではないし、民主主義はそれ自体が黄金のチケットではないかもしれない(少なくとも短期的には)。 では、ほんとうに有効だったものは何か。国際社会が嫌う方法だが、一般市民に力を与えることだ。地元住民主導の草の根の取り組みにこそ暴力を止めるヒントがある。そしてそれは、私たち自身の地域社会やコミュニティ内での対立の解決にも役に立つ。 本書は、20年間の学びがつまった暴力を止めて平和を始めるための実践的ガイドである。 目次 序文(リーマ・ボウイー、2011年ノーベル平和賞受賞者) まえがき 戦争、希望、平和 第一部 可能な和平 第一章 平和の島 第二章 ロールモデル 第二部 ピース・インク 第三章 インサイダーとアウトサイダー 第四章 デザインされた介入 第三部 新しい平和のマニフェスト 第五章 一つひとつの平和 第六章 役割を変える 第七章 自国の前線 謝辞 附録 参考資料 読書会での議論の手引き 授業の手引き 著者プロフィール セヴリーヌ オトセール (セヴリーヌ オトセール) (著/文) 受賞歴のある著述家、平和構築者、研究者であり、コロンビア大学バーナード・カレッジの政治学教授でもある。著書にThe Trouble with the Congo、Peacelandなどがあり、NY Times、The Washington Post、Foreign Affairs、Foreign Policyなどにも寄稿している。20年以上にわたり国際援助の世界に関わり、コロンビア、ソマリア、イスラエル、パレスチナなど12の紛争地域で調査を行ってきた。国境なき医師団の一員としてアフガニスタンやコンゴで、また、米国国連本部で勤務した経験もある。その研究は、いくつかの国連機関、外務省、非政府組織、多くの慈善家や活動家の介入戦略の形成に役立っている。また、ノーベル平和賞受賞者世界サミットや米国下院で講演を行ったこともある。本書The Frontlines of Peace(『平和をつくる方法』)はConflict Research Society(紛争研究会)の「2022年ブック・オブ・ザ・イヤー賞」の最終候補に選ばれた。 山田 文 (ヤマダ フミ) (翻訳) 翻訳者。訳書にウィリアム・アトキンズ『帝国の追放者たち──三つの流刑地をゆく』(柏書房)、マクシミリアン・フォーテ『リビア戦争──カダフィ殺害誌』(感覚社)、フランシス・フクヤマ+マチルデ・ファスティング『「歴史の終わり」の後で』(中央公論新社)、キエセ・レイモン『ヘヴィ──あるアメリカ人の回想録』(里山社)、アミア・スリニヴァサン『セックスする権利』(勁草書房)、などがある。
-

ハイファに戻って/太陽の男たち 文庫
¥968
SOLD OUT
二十年ぶりに再会した息子は別の家族に育てられていた――時代の苦悩を凝縮させた「ハイファに戻って」、密入国を試みる難民たちのおそるべき末路を描いた「太陽の男たち」など、不滅の光を放つ名作群。 著者 ガッサーン・カナファーニー (カナファーニー,G) 1936年パレスチナ生まれ。12歳のときデイルヤーシン村虐殺事件が起こり難民となる。パレスチナ解放運動で重要な役割を果たすかたわら、小説、戯曲を執筆。72年、自動車に仕掛けられた爆弾により暗殺される。
-

パレスチナ戦争 入植者植民地主義と抵抗の百年史
¥3,960
SOLD OUT
アラファートらPLO幹部やサイードなど知識人たちと親交のあったパレスチナ研究大家の初邦訳。膨大なインタビューと、確かな知識に裏打ちされた歴史叙述をベースに、イギリス委任統治政府に追放された伯父や国連に勤務していた父親の話、イスラエルのレバノン侵攻で娘を抱えて逃げた自身の経験など家族史を織り交ぜ、強大な権力に翻弄されてきた民族の一世紀を描き出す。彼らの自決権が否定されてきた先に現在の混迷がある。 目次 序章 第1章 最初の宣戦布告 1917~1939年 第2章 第二の宣戦布告 1947~1948年 第3章 第三の宣戦布告 1967年 第4章 第四の宣戦布告 1982年 第5章 第五の宣戦布告 1987~1995年 第6章 第六の宣戦布告 2000~2014年 終章 パレスチナ戦争の1世紀 訳者あとがき 索引 著者プロフィール ラシード・ハーリディー (ハーリディー ラシード) (著) ラシード・ハーリディー (Rashid Khalidi) 1948年、米国ニューヨーク生まれ。博士。コロンビア大学エドワード・サイード現代アラブ研究教授。ベイルート・アメリカン大学(AUB)で教鞭を執り、2003年より現職。パレスチナ研究機構(IPS)発行Journal of Palestine Studies編集委員。中東近現代史を幅広く専門とする。1982年にイスラエルによるレバノン侵攻に現地で遭遇し、Under Siege: PLO Decision-Making during the 1982 War (Columbia University Press, 1986) を著す。1991~93年にマドリードとワシントンでイスラエルとパレスチナの和平交渉に顧問として参加。Brokers of Deceit: How the U.S. has Undermined Peace in the Middle East (Beacon Press, 2013) など、米国によるパレスチナ問題への関与についても著作多数。 鈴木 啓之 (スズキ ヒロユキ) (訳) 鈴木 啓之 東京大学大学院総合文化研究科スルタン・カブース・グローバル中東研究寄付講座特任准教授。日本学術振興会特別研究員PD(日本女子大学)、日本学術振興会海外特別研究員(ヘブライ大学ハリー・S・トルーマン平和研究所)を経て、2019年9月より現職。著書に『蜂起〈インティファーダ〉――占領下のパレスチナ1967–1993』(東京大学出版会、2020年)、共編著に『パレスチナを知るための60章』(明石書店、2016年)がある。 山本 健介 (ヤマモト ケンスケ) (訳) 山本 健介 静岡県立大学国際関係学部講師。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程(五年一貫制)修了(博士:地域研究)。日本学術振興会特別研究員PD(九州大学)を経て、2021年4月より現職。主著に『聖地の紛争とエルサレム問題の諸相――イスラエルの占領・併合政策とパレスチナ人』(晃洋書房、2020年)がある。 金城 美幸 (キンジョウ ミユキ) (訳) 金城 美幸 立命館大学生存学研究所客員研究員、愛知学院大学等非常勤講師。立命館大学先端総合学術研究科(五年一貫性)修了。博士(学術)。日本学術振興会特別研究員RPD(東京大学)などを経て現在に至る。主な論文に「歴史認識論争の同時性を検討するために――イスラエルと日本」『現代思想』(2018 年5 月号、162–177)、「『虐殺』の物語の奥行き――シャリーフ・カナーアナ、ニハード・ゼイターウィー著『デイル・ヤーシーン』(破壊されたパレスチナ村落シリーズ第4 号)の解題と翻訳」『東京大学東洋文化研究所紀要』(第171 冊、114–188、2017 年)などがある。
-

[再入荷待ち]パレスチナの民族浄化 イスラエル建国の暴力
¥4,290
SOLD OUT
イスラエル人の歴史家である著者は、イギリスやイスラエルの軍事・外交文書や政治家の日記、パレスチナ人の証言など多彩な資料を駆使し、現代世界や中東情勢に影響を与え続ける組織的犯罪の真相を明らかにする。あのときパレスチナ全土でどのように住民は殺され、郷土を追われたのか。なぜ世界はそれを黙認したのか。当時の緊迫した状況や錯綜する思惑、追いつめられる人々の姿を描き、現在の不条理を問う。 目次 プロローグ レッドハウス 第1章 「疑わしい」民族浄化なのか? 第2章 ユダヤ人だけの国家を目指して 第3章 分割と破壊──国連決議181とその衝撃 第4章 マスタープランの仕上げ 第5章 民族浄化の青写真──ダレット計画 第6章 まやかしの戦争と現実の戦争──1948年5月 第7章 浄化作戦の激化──1948年6月~9月 第8章 任務完了──1948年10月~1949年1月 第9章 占領、そしてその醜悪な諸相 第10章 ナクバの記憶を抹殺する 第11章 ナクバの否定と「和平プロセス」 第12章 要塞国家イスラエル エピローグ グリーンハウス 訳者あとがき 索引 著者プロフィール イラン・パペ (パペ イラン) (著) (Ilan Pappé) 1954年、イスラエル・ハイファ市生まれ。ハイファ大学講師を経て、現在、イギリス・エクセター大学教授、同大学パレスチナ研究所所長。イスラエル建国期のパレスチナ現代史を中心としたパレスチナ/イスラエル史研究。1984年に“Britain and the Arab-Israeli Conflict, 1948-1951”で博士号取得。主著に、The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947–1951 (I.B. Tauris, 1992) ; A History of Modern Palestine (Cambridge University Press, 2004) ; The Ethnic Cleansing of Palestine (Oneworld Publications, 2006=本書) などがある。近年は、ヨルダン川西岸地区・ガザ地区の被占領地、イスラエル国内のアラブ・パレスチナ人、アラブ世界出身のユダヤ教徒(アラブ系ユダヤ人)に関する著作も相次いで出版している。日本での講演録として、『イラン・パペ、パレスチナを語る』(つげ書房新社、2008年)がある。 田浪 亜央江 (タナミ アオエ) (訳) 広島市立大国際学部准教授。国際交流基金中東担当専門員、 成蹊大学アジア太平洋研究センター主任研究員などを経て、2017年4月より現職。専攻は中東地域研究、パレスチナ文化研究。単著に『〈不在者〉たちのイスラエル 占領文化とパレスチナ』(インパクト出版会、2008年)、最近の共著として『パレスチナを知るための60章』(明石書店、2016年)、『変革期イスラーム社会の宗教と紛争』(明石書店、2016年)、『中東と日本の針路 「安保法制」がもたらすもの』(大月書店、2016年)等があり、「ミーダーン〈対話のための広場〉」メンバーとしての共編書に『イラン・パペ、パレスチナを語る』(つげ書房新社、2008年)および『〈鏡〉としてのパレスチナ──ナクバから同時代を問う』(現代企画室、2010年)がある。 早尾 貴紀 (ハヤオ タカノリ) (訳) 1973年生まれ。現在、東京経済大学准教授。専攻は社会思想史。 単著に『ユダヤとイスラエルのあいだ』(青土社、2008年)、『国ってなんだろう?』(平凡社、2016年)、共編書に『シオニズムの解剖──現代ユダヤ世界におけるディアスポラとイスラエルの相克』(平凡社、2011年)、『ディアスポラから世界を読む──離散を架橋するために』(明石書店、2009年)、共訳書に、『イラン・パペ、パレスチナを語る』(つげ書房新社、2008年)、サラ・ロイ『ホロコーストからガザへ──パレスチナの政治経済学』(青土社、2009年)、ジョナサン・ボヤーリン/ダニエル・ボヤーリン『ディアスポラの力──ユダヤ文化の今日性をめぐる試論』(平凡社、2008年)、などがある。
-

世界 2023年12月号
¥935
SOLD OUT
【特集1 限界を生きる──超高齢社会の老後とは】 日本の高齢化率が過去最高を記録──人口に占める65歳以上の割合は29%となり、75歳以上が2000万人を超えた。いまや10人に1人が80歳以上である。 戦後日本は「男性稼ぎ主+女性によるケア」というセットによって成り立ってきた「家族」というかたちを、「当たり前のこと」としてきた。急速に進む超高齢化は、この「当たり前」に大きな転換を迫っている。 にもかかわらず、日本社会は変化に対応しきれていない。その結果、「家族」をベースに作られてきた社会保障制度や、住まい、人間関係は、限界点に達してしまっている。もはや私たちにとっては、介護サービスを受けることも、安心して暮らせる家も、気を許して相談できる仲間も、贅沢なものになってしまうのだろうか。 社会をアップデートしない限り、この「限界」は変わらない。 【緊急特集 ガザ 極限の人道危機】 10月7日、ハマスによるイスラエルへの大規模攻撃は、世界に大きな衝撃をもたらした。 近年、類を見ない規模での被害を受けたイスラエルは、反撃を開始。大規模な空爆に加え、パレスチナのガザ地区への電気、食料、水、ガスなどライフラインをストップさせた。無差別の爆撃にさらされ、多数の一般市民(その多くは子どもである)が命を落としている。 ハマスが攻撃に至った背景にはあるのは、長期にわたる和平の失敗ではないか。イスラエルによる56年間もの軍事占領の間、ガザ、そしてヨルダン川西岸の人々は剥き出しの暴力に晒されつづけてきた。2007年のガザ封鎖後、イスラエルは4度もの大規模な軍事攻撃を行った。今年30年の節目を迎えたオスロ合意後も、イスラエル・パレスチナ問題の解決は遠い。 地上侵攻はあってはならない。中東政治の複雑な変化とともに、問題の核心に改めて光を当てたい。失われた命を悼み、殺戮を阻止するために。歴史を指針に考える。 目次 ┃特集 1┃限界を生きる──超高齢社会の老後とは ┗━━━╋…──────────────────────────────── 〈ケアの視点〉 家族のアップデートはいかにして可能か 筒井淳也(立命館大学) 〈介護現場から〉 訪問ヘルパーがいなくなる──問題だらけの介護保険 小島美里(NPO法人「暮らしネット・えん」) 〈家がなくなる〉 深刻化する単身高齢者の住宅問題 葛西リサ (追手門学院大学) 〈社会的課題〉 中高年者の孤立と孤独 小林江里香(東京都健康長寿医療センター) ┏━━━━┓ ┃緊急特集┃ガザ 極限の人道危機 ┗━━━━╋…──────────────────────────────── 〈歴史を紐解く〉 ハマースはなぜイスラエル攻撃に至ったのか 臼杵陽(日本女子大学) 〈読書・観賞日記特別篇〉 人間を描く作品たち 酒井啓子(千葉大学) 〈「ハマスの背後」とは?〉 イランとアメリカ──中東政治の激震のなかで 中西久枝(同志社大学) 〈哲学者が問う〉 哀悼のコンパス──暴力を批判する ジュディス・バトラー(カリフォルニア大学バークレー校)、訳・解説=清水知子 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆注目記事 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〈女性と政治〉 政治とハラスメント──女性議員はなぜ増えないか 濵田真里(Stand by Women代表) 女性を「政治」から遠ざける日本というシステム 安藤優子(ジャーナリスト) ふたつの「壁」──地方議会は変われるか 寺島渉(地域政策塾21) 「変わらない」を変える 第7回──政治家の性別と名前 三浦まり(上智大学) 〈漁業者の苦しみ〉 なぜ、海洋放出だったのか──遠ざけられる漁業復興 濱田武士(北海学園大学) 〈覚悟と提言〉 絶望からのメディア論──なぜ私は朝日を辞めたのか 南彰(琉球新報) 〈普遍的な課題〉 性加害とファン文化の不幸な関係──ジャニーズ問題とわたしたち 田中東子(東京大学) 〈困難な道のり〉 統一教会問題の解決とは何か──「解散命令」請求の限界 櫻井義秀(北海道大学) 〈大国の大罪〉 「蔑まれた地」の声──リビアから考える 福富満久(一橋大学) 〈ウクライナ侵攻一年半〉 プーチン「終わらない戦争」の深層 佐藤親賢(共同通信) 〈ヒトと大地の戦争〉 人新世の惑星政治学とはなにか 前田幸男(創価大学) 〈歴史からの展望〉 グリーン成長・脱成長・ポスト成長──何が異なり、どこへ向かうのか 枝廣淳子(環境ジャーナリスト) 〈治療の現場から〉 終わらないコロナ感染症と後遺症 平畑光一(ヒラハタクリニック)、聞き手=和田秀子 〈「分水嶺 II」番外編〉 次なる「想定外」に備えられるか──コロナ対策専門家の交代 河合香織(ノンフィクション作家) 〈致死処置をめぐって〉 動物の命をめぐる考察──人と動物の関係から 打越綾子(成城大学) 〈人はなぜ惹かれるか?〉 「占い」から社会をまなざす 鏡リュウジ(占星術研究家・翻訳家) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇世界の潮 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇原告全員を水俣病と認めた大阪地裁判決の意味 高峰武 ◇臨時国会召集先送り訴訟──「憲法の番人」の役割を放棄した最高裁 豊秀一 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇SEKAI Review of Books ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇「内なるアウトサイダー」の声は世界にこだまする──林晟一『在日韓国人になる』 森千香子(同志社大学) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●連載 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〈リレー連載〉 隣のジャーナリズム──拍手のないパリコレ 宮智泉(マリ・クレールデジタル編集長) 〈好評連載〉 再録・大江健三郎のことば 第5回 戦後文学から今日の窮地まで 大江健三郎、解題=山本昭宏 ブラック・ミュージックの魂を求めて 第5回──変わりゆく同じもの 中村隆之(早稲田大学) 滅びゆく日本、再生への道 第3回──「大きな絵」描けぬ日本外交 星浩(ジャーナリスト) ●ボナエ・リテラエ──私の読書遍歴 第13回──『ローマ書』 森本あんり(東京女子大学長) ●脳力のレッスン(258)──二一世紀・未来圏の日本再生への構想(その1) 寺島実郎 ●片山善博の「日本を診る」(169)──機関委任事務の亡霊が幅をきかす自治の現場 片山善博(大正大学) ●香港からの通信 第17回──閉ざされた大学キャンパス 鍾剣華(英サリー大学リサーチフェロー) ●気候再生のために 第19回──左右の対立を超えて 江守正多(東京大学) ●日本語のなかの何処かへ 第9回──思い出させる存在 温又柔(作家) ●沖縄(シマ)という窓──「静かな夜を返せ」──四十年越しの嘉手納基地爆音訴訟 親川志奈子(沖縄大学非常勤講師) ●ドキュメント激動の南北朝鮮 (316)──(23・9~10) 編集部 ●民話採光 阿部海太(画家・絵本作家) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○読者投句・岩波俳句 選・文=池田澄子(俳人) ○アムネスティ通信 ○読者談話室 ○デザイン 赤崎正一 + 佐野裕哉 (協力=国府台さくら)
-

ガザに地下鉄が走る日
¥3,520
SOLD OUT
イスラエル建国とパレスチナ人の難民化から70年。高い分離壁に囲まれたパレスチナ・ガザ地区は「現代の強制収容所」と言われる。そこで生きるとは、いかなることだろうか。 ガザが完全封鎖されてから10年以上が経つ。移動の自由はなく、物資は制限され、ミサイルが日常的に撃ち込まれ、数年おきに大規模な破壊と集団殺戮が繰り返される。そこで行なわれていることは、難民から、人間性をも剥奪しようとする暴力だ。 占領と戦うとは、この人間性の破壊、生きながらの死と戦うことだ。人間らしく生きる可能性をことごとく圧殺する暴力のなかで人間らしく生きること、それがパレスチナ人の根源的な抵抗となる。 それを教えてくれたのが、パレスチナの人びとだった。著者がパレスチナと関わりつづけて40年、絶望的な状況でなお人間的に生きる人びととの出会いを伝える。ガザに地下鉄が走る日まで、その日が少しでも早く訪れるように、私たちがすることは何だろうかと。 目次 第1章 砂漠の辺獄 第2章 太陽の男たち 第3章 ノーマンの骨 第4章 存在の耐えられない軽さ 第5章 ゲルニカ 第6章 蠅の日の記憶 第7章 闇の奥 第8章 パレスチナ人であるということ 第9章 ヘルウ・フィラスティーン? 第10章 パレスチナ人を生きる 第11章 魂の破壊に抗して 第12章 人間性の臨界 第13章 悲しい苺の実る土地 第14章 ガザに地下鉄が走る日 あとがき 著者プロフィール 岡真理 (オカマリ) (著/文) 1960年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科教授。専門は現代アラブ文学、パレスチナ問題、第三世界フェミニズム思想。著書に『記憶/物語』(岩波書店)、『彼女の「正しい」名前とは何か』、『棗椰子の木陰で』(以上、青土社)、『アラブ、祈りとしての文学』、『ガザに地下鉄が走る日』(以上みすず書房)ほか。訳書にエドワード・サイード『イスラム報道 増補版』(共訳、みすず書房)、サラ・ロイ『ホロコーストからガザへ』(共訳、青土社)、ターハル・ベン=ジェルーン『火によって』(以文社)、アーディラ・ライディ『シャヒード、100の命』(インパクト出版会)、サイード・アブデルワーヒド『ガザ通信』(青土社)ほか。2009年から平和を目指す朗読集団「国境なき朗読者たち」を主宰し、ガザをテーマとする朗読劇の上演活動を続ける。 Kindle→https://amzn.to/40EAcO1
-

[新装版刊行待ち]ホロコーストからガザへ パレスチナの政治経済学
¥2,860
SOLD OUT
*近いうちに新装版が刊行されるようです。情報上がり次第こちらも更新します 「パレスチナ問題」を経済学的に分析し、世界的に注目される著者が明らかにするイスラエルの占領の実態と国際社会の援助の行方。ホロコースト生存者の娘という出自から問う、人間の記憶と倫理への思考。 目次 ガザ地区とパレスチナの概要およびサラ・ロイの仕事 もしガザが陥落すれば… ガザ以前、ガザ以後―イスラエル‐パレスチナ問題の新たな現実を検証する 「対テロ戦争」と二つの回廊 ホロコーストからパレスチナ‐イスラエル問題へ “新しい普遍性”を求めて―ポスト・ホロコースト世代とポスト・コロニアル世代の対話 著者紹介 ロイ,サラ[ロイ,サラ][Roy,Sara] 1955年アメリカ生まれ。政治経済学。ハーバード大学中東研究所上級研究員。パレスチナ、とくにイスラエルによるガザ地区の占領問題の政治経済学的研究で世界的に知られる 岡真理[オカマリ] 1960年生まれ。現代アラブ文学、第三世界フェミニズム思想。京都大学大学院人間・環境学研究科教授 小田切拓[オダギリヒロム] 1968年生まれ。フリージャーナリスト。報道・経済番組制作後、イスラエル/パレスチナを中心に取材を行なう。とくにガザ地区、隔離壁、経済援助の問題を掘り下げた報道で知られる 早尾貴紀[ハヤオタカノリ] 1973年生まれ。社会思想史。東京大学COE「共生のための国際哲学教育研究センター」研究員、東京経済大学他非常勤講師
-

[再入荷待ち]パレスチナを知るための60章
¥2,200
SOLD OUT
1948年のイスラエル建国以降、中東の火種となってきたパレスチナ。70年近くに及ぶ難民キャンプの暮らし、あるいは「分離壁」に代表されるイスラエルの抑圧的な政策の下にあって、なおアイデンティティを求め続けるパレスチナの人々を描く。 目次 はじめに Ⅰ パレスチナ イメージと実像 第1章 パレスチナとはどこか――アイデンティティの拠り所を考える 第2章 世界に離散するパレスチナ人――繰り返される移動 第3章 パレスチナ人はどんなところに住んでいるのか――難民キャンプから「持ち家」へ 第4章 パレスチナ人は何を食べているのか――オスマン時代から続く伝統的食文化 【コラム1】パレスチナの家庭料理――ひと手間が引き出すおいしさと家庭の誇り 第5章 パレスチナのイエと社会――パレスチナ人のアイデンティティ/39 【コラム2】結婚式 第6章 キリスト教徒として生きる人々――多様な宗教文化 第7章 ドゥルーズ派の人々――イスラエルとアラブのはざまで 【コラム3】「3652年間この地に生きる」サマリア人 第8章 失われた多様性――つくられた「マイノリティ問題」 第9章 ハリウッド映画のパレスチナ人像――捏造される「悪いアラブ」 【コラム4】映画『ミュンヘン』――9・11後のアメリカ社会とパレスチナ問題 第10章 日本人キリスト教徒のパレスチナ・イメージ――パレスチナへの無関心は何によるのか 第11章 『オリエンタリズム』の衝撃――日本でのエドワード・サイード受容 Ⅱ 歴史 第12章 オスマン帝国時代のパレスチナ――蒔かれた紛争の種 第13章 イギリスによる支配――パレスチナ委任統治期 【コラム5】ド・ブンセン委員会――イギリス中東分割政策の青写真 第14章 パレスチナ難民はなぜ生まれたか――忘却されるナクバ 第15章 イスラエルに残ったパレスチナ人――差別・分断と新たな機運 第16章 アラブ・ナショナリズムとパレスチナ・ナショナリズム――シュカイリー初代PLO議長 第17章 パレスチナ解放運動の昂揚――ヤーセル・アラファートとパレスチナ解放機構(PLO) 第18章 アラブ諸国との軋轢――黒い9月とレバノン内戦 第19章 石の蜂起――幻の独立宣言から孤立へ 【コラム6】アメリカン・コロニーの変遷 第20章 オスロ和平プロセス――誕生・展開・挫折 第21章 なぜパレスチナ人はハマースを支持するのか――暫定自治政府の限界 【コラム7】アフマド・ヤースィーン――創設者が描いたハマースの原点と広がり Ⅲ 生活と文化 第22章 ヘブロンの都市生活――イスラーム的伝統の復興 第23章 オリーブと生きる――土地とのつながり、人々の暮らしの象徴 【コラム8】パレスチナのビール・ワイン 第24章 パレスチナの刺繍――モチーフが映し出すパレスチナ 【コラム9】パレスチナの衣装 第25章 難民女性ガーダ――占領と強権の圧力に抗する 第26章 「同胞の“痛み”を我が“痛み”として生きる」――人権活動家ラジ・スラーニとその活動 第27章 タブーに挑む――パレスチナ人ジャーナリストの挑戦 【コラム10】パレスチナ映画――パレスチナ人の実存の視覚的オルタナティブ 第28章 パレスチナ演劇――「失われた」言葉を取り戻す 【コラム11】パレスチナの踊り「ダブケ」 第29章 パレスチナ文学――ナクバから生まれた言葉の力 【コラム12】言葉の「ナクバ」――ヘブライ語で書くパレスチナ人作家 第30章 ウード弾きたちの挑戦――伝統音楽から新しい地平へ 第31章 ポピュラー音楽――革命歌からラップまで 【コラム13】パレスチナ系アメリカ人のコメディアン Ⅳ 世界の中のパレスチナ 第32章 国連の難民救済事業――UNRWAの活動 【コラム14】第一次中東戦争に参加した北アフリカ義勇兵 第33章 アメリカのパレスチナ関与――歴代大統領はパレスチナをどう見てきたか 第34章 ソ連・ロシアの対パレスチナ政策――放置されるロシアの飛び地 第35章 パレスチナ国家の承認――紛争解決の模索 第36章 大国エジプトの変節――宗教、帝国主義、民族主義、そして新しい時代へ 【コラム15】ガザ難民――二人の女子学生と出会って 第37章 隣国ヨルダンの歩み――紛争の展開と国家像の模索 第38章 シリア・レバノンのパレスチナ人――安全と未来を求めて 【コラム16】「イスラーム国」とパレスチナ 第39章 大義を掲げる湾岸諸国――アラブの同胞か、他人事か 第40章 聖都エルサレム――占領下の生活空間 第41章 イスラエルとパレスチナの非対称性――国家主体と非国家主体 【コラム17】パレスチナを旅行する Ⅴ 経済と社会 第42章 パトロン・クライアント関係――近代パレスチナ社会の支配層 第43章 水と土地――権利あるいは空間をめぐる問題 第44章 ヨルダン川西岸の産業――実地調査から見える現状と課題 【コラム18】パレスチナの伝統工芸品 第45章 パレスチナの農業――資源と市場への限られたアクセス 第46章 農村の生活――パレスチナの文化を育む農村の暮らし 第47章 通貨と金融――オスロ合意は何をもたらしたか 第48章 公共部門と公共サービス――あまりに不安定な現実 【コラム19】アンマーンの交通事情と難民 第49章 ワクフ――翻弄されたイスラーム的信託制度 第50章 難民の初等・中等教育――UNRWAの教育と育つ人材 第51章 占領下で学ぶ――大学設立にかけた願いと挑戦 【コラム20】記録し、発信する――パレスチナ研究機構の挑戦 第52章 変遷する障害者福祉――誰も置き去りにしない社会に向けて 【コラム21】分離壁 Ⅵ パレスチナと日本 第53章 対パレスチナ外交――人的交流から資金援助まで 【コラム22】アラファートの日本訪問とIPTIL 第54章 日本に来たパレスチナ人――パレスチナ駐日代表アブドゥルハミードと日本 【コラム23】PLO東京事務所と日本 【コラム24】李香蘭とパレスチナ 【コラム25】「天よ、我に仕事を与えよ」――自己否定と弱者の政治=軍事再考 第55章 日本の経済支援――国際協調と地域安定への試み 第56章 日本の医療支援――パレスチナに根づいた支援 第57章 市民社会による支援――1万キロを越えての連帯とその課題 第58章 イスラエル・ボイコット運動――パレスチナにおける「アパルトヘイト」廃絶への挑戦 第59章 フェアトレード――生活の糧としての伝統工芸 第60章 日本のジャーナリズムとパレスチナ――エルサレム特派員が見たオスロ合意 【コラム26】戦前・戦中の日本とパレスチナ パレスチナを知るための文献・情報ガイド
-

スパイスとセーファースペース
¥770
SOLD OUT
スパイスを使ったチャイをみんなでつくって飲みながらセーファースペースについて考えるイベント「スパイスとセーファースペース」をまとめたzine。 本書の主な内容は、イベント後に行った座談会の内容をまとめたものです。新刊書店「本屋メガホン」を運営する和田、アーティスト・コレクティブ「ケルベロス・セオリー」のメンバーである山もと、デザインを担当する浦野のイベント企画者3人に加え、イベントに参加してくれた、東京都内のチェーン書店に勤める皆本夏樹さんと、東京都内で一箱本屋として活動する「Castellu」の店主の5名で、イベントを終えた感想やセーファースペースをめぐるそれぞれの実践、問題意識などについて話し合いました。 “イベントにおいて共通の問題意識として話し合われたのは、「セーファースペースについてまとまった資料や文献が少ない」ことでした。セーファースペースという概念そのものが、常により良い状態を模索し、そのあり方を更新し続けることを前提としているため、その都度立ち返ることのできる指針のようなものの存在は誰にとっても必要なはずだと考え、今回のイベントの様子をzineとしてまとめることにしました。本書が、これからセーファースペースについて考えたいと思っている人にとっての道標となったり、すでに実践している人にとってその考えを広げるような役割を果たすことができれば嬉しいです。”(「はじめに」より) *セーファースペースとは 「差別や抑圧、あるいはハラスメントや暴力といった問題を、可能な限り最小化するためのアイディアの 一つで、『より安全な空間』を作る試み」(『生きるためのフェミニズム パンとバラと反資本主義』堅田香緒里/タバブックス/2021年) のこと。様々なジェンダーや階級、言語やセクシュアリティを有する人々が一同に集まる社会運動の場において、そういった社会的背景の違いから生まれる差別や軋轢をいかに最小化するか、という問題意識から生まれたこの概念は、すべての人にとって完全に安全な空間など存在しないという前提を共有しつつ、それでも「“より安全な空間”を共同して作り続けていくこと」を目指す試みであることから、safeでもsafestでもなくsafer(=より安全な)という比較級が用いられています。 発行:本屋メガホン 編集:山もといとみ 浦野貴識 印刷:when press https://www.whenpress.com 判型:W105mm×H250mm 12ページ
-
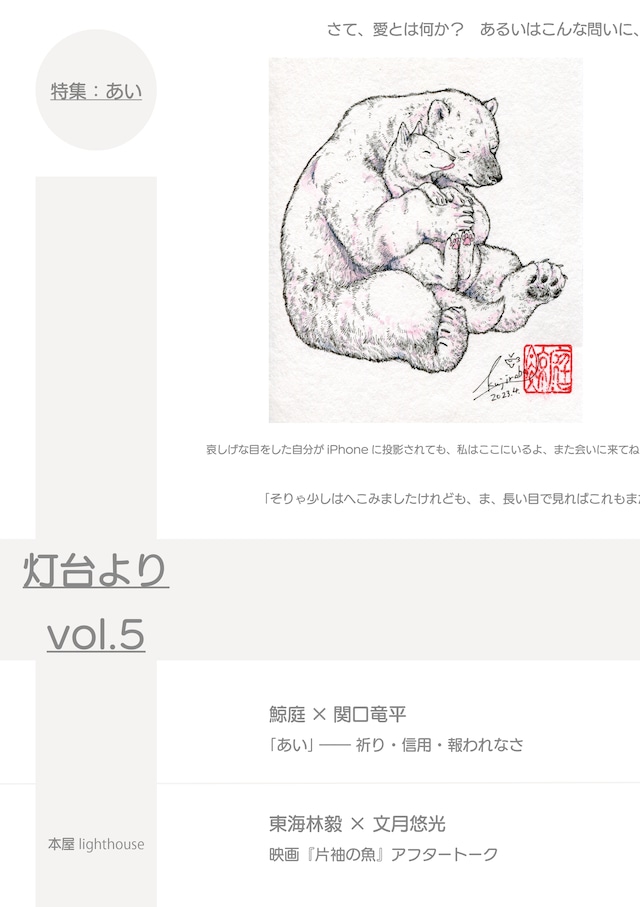
灯台より vol.5 特集:あい
¥1,320
SOLD OUT
特集:あい 本屋lighthouseが定期的に刊行しようと思いつつも不定期に刊行している文芸誌的なサムシング、『灯台より』のvol.5です。 今号より大増量でお送りします。 気分的には第2期的な感じです。 *PDF版も刊行しています 目次 鹿子裕文 p2 「真っ赤な夜のブルース」 #5 損してナンボのイマジン 橋本亮二 p6 「本を抱えて会いにいく」 #5 あいを受けとる 僕のマリ p12 「まほろばハイウェイ」 #3 空前のゾウブーム 対談 p16 鯨庭×関口竜平 「あい」 ―― 祈り・信用・報われなさ 梶本時代 p42 「梶本時代の人生あじゃぱ節」 #5 恥の海より エッセイ p48 ひらいめぐみ 曖昧 エッセイ p52 小原 晩 あの他人 対談 p54 東海林毅×文月悠光 映画『片袖の魚』アフタートーク ルポ p78 中村佳太 パートナーシップ制度の導入を求める陳情が逆転採択されるまでの経緯。 とそこで気づいた問題点。 エッセイ p90 水上 文 ジャンピング・あい エッセイ p96 小澤みゆき ポケモンLEGENDSアルセウスのかんそう 守屋 信 p102 「十九年」 #5 ゆっくりおやすみ、また明日ね 編集後記:灯台守の日誌 p112 「現代 未刊のプロジェクト」 #5 *休載 本間 悠 「書店員です。兼業酒婦です。」 仲西森奈 連載小説 「どこに行ってもたどり着く場所」 仕様 A5版・116p フルカラー 表紙イラスト:鯨庭 刊行日:2023年7月10日
-

[PDF版]「灯台より」vol.5 特集:あい *ALTあり
¥660
SOLD OUT
こちらはPDFデータ版です。 ファイルが2つありますが、ひとつはそのままPDFとして読むもの。 もうひとつはお手持ちの電子書籍リーダーにて読める形式(epub)となっています。 ただ、リフロー形式には対応していませんのでご了承ください。 また、PDF形式のものにはALTをつけています。読み上げ機能などを設定してご活用くださいませ。 本屋lighthouseが定期的に刊行しようと思いつつも不定期に刊行している文芸誌的なサムシング、『灯台より』のvol.5です。 今号より大増量でお送りします。 気分的には第2期的な感じです。 目次 鹿子裕文 p2 「真っ赤な夜のブルース」 #5 損してナンボのイマジン 橋本亮二 p6 「本を抱えて会いにいく」 #5 あいを受けとる 僕のマリ p12 「まほろばハイウェイ」 #3 空前のゾウブーム 対談 p16 鯨庭×関口竜平 「あい」 ―― 祈り・信用・報われなさ 梶本時代 p42 「梶本時代の人生あじゃぱ節」 #5 恥の海より エッセイ p48 ひらいめぐみ 曖昧 エッセイ p52 小原 晩 あの他人 対談 p54 東海林毅×文月悠光 映画『片袖の魚』アフタートーク ルポ p78 中村佳太 パートナーシップ制度の導入を求める陳情が逆転採択されるまでの経緯。 とそこで気づいた問題点。 エッセイ p90 水上 文 ジャンピング・あい エッセイ p96 小澤みゆき ポケモンLEGENDSアルセウスのかんそう 守屋 信 p102 「十九年」 #5 ゆっくりおやすみ、また明日ね 編集後記:灯台守の日誌 p112 「現代 未刊のプロジェクト」 #5 *休載 本間 悠 「書店員です。兼業酒婦です。」 仲西森奈 連載小説 「どこに行ってもたどり着く場所」 仕様 A5版・116p フルカラー 表紙イラスト:鯨庭 刊行日:2023年7月10日
-

ユートピアとしての本屋 暗闇のなかの確かな場所
¥1,870
SOLD OUT
*おぺんのらくがきをご希望のかたは備考欄にてその旨お知らせください\(•ө•)/ 以下、出版社作成の紹介文です。なんか恥ずかしい。 ---------------------------------------------------------------------------------- たった一人で独立書店を立ち上げ、反差別をかかげた果敢な発言でも注目される「本屋lighthouse」の若き店主による単著。知への信頼が揺らぐ時代に、誰もが生きられる空間をつくるための実践と思考の書。 [目次] はじめに 1 本屋になるまでの話 2 メディア/クリエイターとしての本屋 3 ひとりの人間としての本屋 4 本屋にとっての反ヘイト・反差別とは 5 差別は道徳では解決しない 6 出版業界もまた差別/支配構造の中にある 7 セーファースペースとしての本屋 8 教室としての本屋 9 ユートピアとしての本屋 おわりに Kindle→https://amzn.to/3LhD8tD
-

まばゆい
¥1,650
SOLD OUT
僕のマリ、待望のエッセイ集。 「苦しくて甘いよろこび 色あせることのない思い出たち」 〈植本一子さん帯文〉 書くことは自分を救うことーーそう言い切る彼女に賛同する。 私たちは似ているところがある。書かずにはいられないのだ。良いことも悪いことも、たとえ大事な人を傷つけても。 自分のために、誰かのために、きっと今日も書いている。 『常識のない喫茶店』(柏書房)にて商業デビュー、発売すぐに重版もかかるなどその実力を見せつけている僕のマリのエッセイ集。『喫茶店』に至るまでの彼女の人生を振り返る1冊でもあり、彼女の「書くこと」に関する〈核〉のようなものも見えてくる内容となりました。読後にはタイトルの『まばゆい』に込められた想いが、自ずと沁み入ってくると思います。『常識のない喫茶店』とあわせて読んでもらえるとうれしいです。 〈目次〉 まえがき 生活 注意力散漫 愛を飼う きょうだい 緘黙のファンファーレ 青さと音楽 野崎さんのこと ほろ酔い 終わりのない友情 いままでのこと、これからのこと お母さんへ あとがき 奥付・著者プロフィール 写真(カラー) 〈仕様〉 B6変形 仮フランス装 表紙用紙 クラシックリネン129kg (雪) 見返し タント100kg グレー(B-5) 帯 クロマティコトレーシング(白) 本文用紙 b7バルキー73.0kg 128p(巻末16pはカラー写真) 〈著者プロフィール〉 僕のマリ 1992年福岡県生まれ。2018年活動開始。同年、短編集『いかれた慕情』を発表。2021年には柏書房より『常識のない喫茶店』を刊行。犬が好き。 Twitter:@bokunotenshi_ 品子(写真) 1992年生まれのいて座。2016年に写真集「街の灯」を制作。現在、喫茶店で働きながら気ままに写真を撮っています。

-

おぺん選書便(3冊/5500円くらいのやつ)
¥5,500
SOLD OUT
本3冊+lighthouseロゴトートバッグ1つのセットです。 本3冊でだいたい5500円(税込)くらいになるように選書します。 設定金額に届かない分をトートバッグで吸収するスタイルです(トートバッグ単体は1000円+税で販売中)。 備考欄に ・トートバッグの色(ナチュラル/ネイビー) ・読みたいジャンルやテーマ(3つまで) ・くわえてNGのジャンルやテーマ、作家などがあれば(これは読みたくない!というものを知れたほうがありがいもので……) ・そのほか細かい希望があれば遠慮なくどうぞ あたりをご記入ください。 この本は入れてくれ、という「注文」もなんなりと。 そのほか質問などあればお問い合わせくださいませ。 *1万円選書のサービス「ブックカルテ」にも参加していますので、そちらのご利用も大歓迎です https://bookkarte.com

-

ゆさぶるカルチュラル・スタディーズ
¥2,530
SOLD OUT
コギャル、都会と地方、モバイルメディア、F1、音楽、フェミニズム、漫画、ボディ・プロジェクト、社会運動、アート等、多様な文化の側面から逆なでに読み解くカルチュラル・スタディーズ入門。またカルチュラル・スタディーズとはなにか? 今までのカルチュラル・スタディーズの軌跡を概観しつつ、これからの課題についても示唆した意欲作。 目次 第1章 モバイルメディアの殻・繭・棘(ケイン樹里安) 第1節 殻と繭 第2節 監視vsチル 第3節 棘 第4節 夢と悪夢のスマートシティ 第5節 全力と諦念 研究コトハジメ:深夜のマクド 第2章 「ここ」ではない「どこか」へ:都会と田舎をめぐる若者の物語を移動/越境から考える(清水友理子) 第1節 移動は「田舎から都会へ」から「都会から田舎へ」へ? 第2節 どこへでも行ける?フラット化=ポスト・アーバン化する社会 第3節 さらに遠くへ、あるいは、ずっと地元のままで? 第4節 「田舎vs都会」を超えて 研究コトハジメ:フィールドに出る一歩手前の準備:五感を働かせる 第3章 奪い・奪われ・奪い返すスタイル:サブカルチャーとしてコギャルを読み解く(関根麻里恵) 第1節 サブカルチャーとは何か 第2節 コギャルというサブカルチャー 第3節 スタイルをめぐる闘争と交渉 第4節 進化する(コ)ギャルスタイル 研究コトハジメ:『GALS!』が教えてくれたこと:フィクション作品が与えた影響について 第4章 フレンチポップのなかのジェンダー構造:ラブソングにおける対抗的実践を読みとる(中條千晴) 第1節 フレンチポップのラブソングに見る男女の関係性 第2節 現代フランスとフェミニズム 第3節 アンジェルの『Balance ton quoi』に見る実践 第4節 結論(づけないために) 研究コトハジメ:ポピュラー音楽を分析する 第5章 レズビアンの剥片化に抗して:『作りたい女と食べたい女』を読む(竹田恵子) 第1節 セクシュアル・マイノリティの存在・アイデンティティ・権利 第2節 ポルノ、そして「百合」から「レズビアン」の表象へ 第3節 「レズビアン」存在の剥片化に抗して 研究コトハジメ:「自分のありかたを発明する」 第6章 スポーツのファンダム:クルマ文化とF1(加藤昌弘) 第1節 参加型文化としてのF1のファンダムを捉え直す 第2節 F1と映像メディア 第3節 グローバルなスポーツはナショナリズムを変えるのか 第4節 グローバル資本主義と格差の問題 第5節 女性とF1のかかわり方 第6節 F1を「見る」ことと「遊ぶ」こと 研究コトハジメ:「好き」を仕事(研究)にすべきか 第7章 創られる理想、作られる身体:私たちはどのようにボディ・プロジェクトへと向かうのか(竹﨑一真) 第1節 身体をどうとらえるか? 第2節 ポスト工業社会と身体の理想 第3節 コンフィデンス・カルチャーとしてのボディ・プロジェクト 第4節 身体から社会をゆさぶる 研究コトハジメ:記号であり生モノでもある筋肉 第8章 「黒い暴動」:移民たちはなぜ踊り始めたのか(稲垣健志) 第1節 奴隷たちの隠れた抵抗 第2節 「ロンドンは僕のための場所」か?:イギリスにおけるレイシズム 第3節 カーニヴァルを再創造する 第4節 「危機」を取り締まる 研究コトハジメ:「真似る」という文化実践 第9章 『三つ目がとおる』と失われた過去の〈場所〉マヤ文明(鋤柄史子) 第1節 二つの表象:三つ目とマヤ文明 第2節 マヤ文明表象とポストコロニアリズム 第3節 戦後日本のオカルトカルチャーと手塚のジレンマ 研究コトハジメ:ゆさぶる「目」を身につける 第10章 オンライン空間の文化と社会参加:韓国におけるウトロ地区支援の一端(全ウンフィ) 第1節 オンライン空間に浮かび上がる「社会」 第2節 文化を基盤とする社会空間 第3節 遊びの空間を橋渡しする人々 第4節 サブカルチャーの空間性からみる社会参加 研究コトハジメ:場所に込められたもの・こと 第11章 人と歴史をつなげる現代アート:現代在日コリアン美術を例に(山本浩貴) 第1節 現代アートとは何か 第2節 ソーシャリー・エンゲージド・アート 第3節 リレーショナル・アートと敵対 第4節 現代在日コリアン美術:呉夏枝と琴仙姫 第5節 現代アートの力と可能性 研究コトハジメ:現代アートを「研究」する 第12章 文化の「遺産化・財化」に抗う文化実践:「内灘闘争――風と砂の記憶――」展をめぐって(稲垣健志) 第1節 内灘闘争 第2節 文化を「遺産化・財化」するということ 第3節 「風と砂の記憶」展2018・2021 第4節 それがアートである理由 研究コトハジメ:ぶらぶらのススメ 第13章 「カルスタ」を逆なでに読む:カルチュラル・スタディーズをゆさぶるために(稲垣健志) 第1節 カルスタの「誕生」 第2節 カルチュラル・スタディーズの翻訳:カルスタはパンクに出会ったのか? 第3節 カルチュラル・タイフーンの発生:台風はどこに上陸するのか? 第4節 カルスタをどう逆なでるか 研究コトハジメ:それでもやはり 著者プロフィール 稲垣 健志 (イナガキ ケンジ) (著/文 | 編集) 金沢美術工芸大学美術工学部准教授。 主著(論文)に、‘Radicals Strike Back: A Memorandum for the Cultural Studies of Black Radicalism in Britain’『金沢美術工芸大学紀要』第65 号(2021 年)、「カルチュラル・スタディーズを裏 返す―A. シヴァナンダンをめぐるいくつかの断章」『年報カルチュラル・スタディーズ』Vol. 10(2022 年)など。訳書に、ガルギ・バ タチャーリャ『レイシャル・キャピタリズムを再考する―再生産と生存に関する諸問題―』(人文書院、2023 年)。