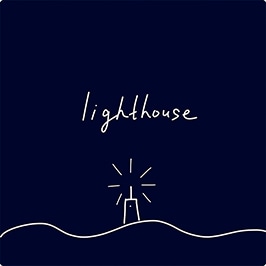こちらのウェブストアは運営停止しています。
購入は新ストア(以下のボタンをクリック)よりお願いします。
*Tシャツなどのグッズはこちらで購入可能です。
-

ガザとは何か パレスチナを知るための緊急講義
¥1,540
SOLD OUT
【緊急出版!ガザを知るための「まず、ここから」の一冊】 2023年10月7日、ハマース主導の越境奇襲攻撃に端を発し、イスラエルによるガザ地区への攻撃が激化しました。 長年パレスチナ問題に取り組んできた、 パレスチナ問題と現代アラブ文学を専門とする著者が、 平易な語り口、そして強靭な言葉の力によって さまざまな疑問、その本質を明らかにします。 今起きていることは何か? パレスチナ問題の根本は何なのか? イスラエルはどのようにして作られた国? シオニズムとは? ガザは、どんな地域か? ハマースとは、どのような組織なのか? いま、私たちができることは何なのか? 今を知るための最良の案内でありながら、 「これから私たちが何を学び、何をすべきか」 その足掛かりともなる、 いま、まず手に取りたい一冊です。 ■目次■ ■第1部 ガザとは何か 4つの要点/イスラエルによるジェノサイド/繰り返されるガザへの攻撃/イスラエルの情報戦/ガザとは何か/イスラエルはどう建国されたか/シオニズムの誕生/シオニズムは人気がなかった/なぜパレスチナだったのか/パレスチナの分割案/パレスチナを襲った民族浄化「ナクバ」/イスラエル国内での動き/ガザはどれほど人口過密か/ハマースの誕生/オスロ合意からの7年間/民主的選挙で勝利したハマース/抵抗権の行使としての攻撃/「封鎖」とはどういうことか/ガザで起きていること/生きながらの死/帰還の大行進/ガザで増加する自殺/「国際法を適用してくれるだけでいい」 ■第2部 ガザ、人間の恥としての 今、目の前で起きている/何度も繰り返されてきた/忘却の集積の果てに/不均衡な攻撃/平和的デモへの攻撃/恥知らずの忘却/巨大な実験場/ガザの動物園/世界は何もしない/言葉とヒューマニティ/「憎しみの連鎖」で語ってはいけない/西岸で起きていること/10月7日の攻撃が意味するもの/明らかになってきた事実/問うべきは「イスラエルとは何か」/シオニズムとパレスチナ分割案/イスラエルのアパルトヘイト/人道問題ではなく、政治的問題 ■質疑応答 ガザに対して、今私たちができることは?/無関心な人にはどう働きかければいい?/パレスチナ問題をどう学んでいけばいい?/アメリカはなぜイスラエルを支援し続けるのか?/BDS運動とは何? ■付録 もっと知るためのガイド(書籍、映画・ドキュメンタリー、ニュース・情報サイト) パレスチナ問題 関連年表 本書は、10月20日京都大学、10月23日早稲田大学で開催された緊急セミナーに加筆修正を加えたものです。 著者 岡 真理 1960年生まれ。東京外国語大学大学院修士課程修了。在モロッコ日本国大使館専門調査員、大阪女子大学人文社会学部講師、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を経て、早稲田大学文学学術院教授。専攻は現代アラブ文学・第三世界フェミニズム思想。 Kindle→https://amzn.to/3txaPS4
-
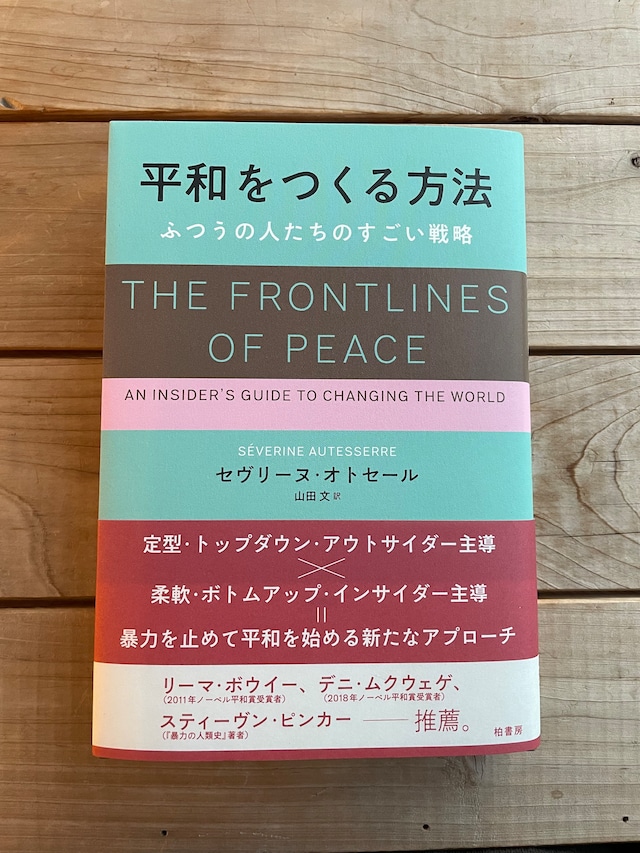
平和をつくる方法 ふつうの人たちのすごい戦略
¥2,860
SOLD OUT
★紛争研究会が選ぶ「2022年ブック・オブ・ザ・イヤー賞」最終候補作 ★寄せられた賛辞の一部 「平和は可能だがむずかしい。…大きなアイデアと現場のファクト、その両方を知る専門家に耳を傾けることが欠かせない。『平和をつくる方法』は人類の最も崇高な試みについて新たな洞察を与えてくれる」──スティーヴン・ピンカー(『暴力の人類史』著者) 「セヴリーヌ・オトセールは、コンゴであれ、コロンビアであれ、アメリカであれ、日々、地域社会で暴力を減らすために努力している普通の女性や男性の物語を語る。読者に行動を促す、魅惑的で感動的な物語だ」──デニ・ムクウェゲ(2018年ノーベル平和賞受賞者) 「『平和をつくる方法』は、ありふれた国際政治の本ではない。まわりの世界の見方を変える一冊だ」──リーマ・ボウイー(2011年ノーベル平和賞受賞者) ★内容 平和構築という言葉は、私たちが何度も耳にした物語を想起させるかもしれない。ある地域で暴力が発生すると、国連が介入し、ドナーが多額の支援を約束し、紛争当事者が協定に署名して、メディアが平和を称える。そして数週間後、ときには数日後に、暴力が燃えあがる──そのような物語。 はたして、私たちに持続可能な平和を築くことなど可能だろうか? 可能だとすればどのように? そうした問いに答えるのが本書である。 著者は、善意にもとづくが本質的な欠陥を抱える「ピース・インク」と彼女が名付けるものについて──その世界に身を浸しながら(参与観察)──考察する。最も望ましくない状況であっても平和は育まれることを証明するために。 そのため、従来とは異なる問いの立て方もする。つまり、〈不思議なのは…紛争解決の取り組みが失敗するのはなぜか、ではない。ときどき大成功を収めるのはなぜか、だ〉。 そう、多くの政治家や専門家が説くのとは反対に、問題に大金を投じても解決策になるとはかぎらない。選挙で平和が築かれるわけではないし、民主主義はそれ自体が黄金のチケットではないかもしれない(少なくとも短期的には)。 では、ほんとうに有効だったものは何か。国際社会が嫌う方法だが、一般市民に力を与えることだ。地元住民主導の草の根の取り組みにこそ暴力を止めるヒントがある。そしてそれは、私たち自身の地域社会やコミュニティ内での対立の解決にも役に立つ。 本書は、20年間の学びがつまった暴力を止めて平和を始めるための実践的ガイドである。 目次 序文(リーマ・ボウイー、2011年ノーベル平和賞受賞者) まえがき 戦争、希望、平和 第一部 可能な和平 第一章 平和の島 第二章 ロールモデル 第二部 ピース・インク 第三章 インサイダーとアウトサイダー 第四章 デザインされた介入 第三部 新しい平和のマニフェスト 第五章 一つひとつの平和 第六章 役割を変える 第七章 自国の前線 謝辞 附録 参考資料 読書会での議論の手引き 授業の手引き 著者プロフィール セヴリーヌ オトセール (セヴリーヌ オトセール) (著/文) 受賞歴のある著述家、平和構築者、研究者であり、コロンビア大学バーナード・カレッジの政治学教授でもある。著書にThe Trouble with the Congo、Peacelandなどがあり、NY Times、The Washington Post、Foreign Affairs、Foreign Policyなどにも寄稿している。20年以上にわたり国際援助の世界に関わり、コロンビア、ソマリア、イスラエル、パレスチナなど12の紛争地域で調査を行ってきた。国境なき医師団の一員としてアフガニスタンやコンゴで、また、米国国連本部で勤務した経験もある。その研究は、いくつかの国連機関、外務省、非政府組織、多くの慈善家や活動家の介入戦略の形成に役立っている。また、ノーベル平和賞受賞者世界サミットや米国下院で講演を行ったこともある。本書The Frontlines of Peace(『平和をつくる方法』)はConflict Research Society(紛争研究会)の「2022年ブック・オブ・ザ・イヤー賞」の最終候補に選ばれた。 山田 文 (ヤマダ フミ) (翻訳) 翻訳者。訳書にウィリアム・アトキンズ『帝国の追放者たち──三つの流刑地をゆく』(柏書房)、マクシミリアン・フォーテ『リビア戦争──カダフィ殺害誌』(感覚社)、フランシス・フクヤマ+マチルデ・ファスティング『「歴史の終わり」の後で』(中央公論新社)、キエセ・レイモン『ヘヴィ──あるアメリカ人の回想録』(里山社)、アミア・スリニヴァサン『セックスする権利』(勁草書房)、などがある。
-

[再入荷待ち]パレスチナの民族浄化 イスラエル建国の暴力
¥4,290
SOLD OUT
イスラエル人の歴史家である著者は、イギリスやイスラエルの軍事・外交文書や政治家の日記、パレスチナ人の証言など多彩な資料を駆使し、現代世界や中東情勢に影響を与え続ける組織的犯罪の真相を明らかにする。あのときパレスチナ全土でどのように住民は殺され、郷土を追われたのか。なぜ世界はそれを黙認したのか。当時の緊迫した状況や錯綜する思惑、追いつめられる人々の姿を描き、現在の不条理を問う。 目次 プロローグ レッドハウス 第1章 「疑わしい」民族浄化なのか? 第2章 ユダヤ人だけの国家を目指して 第3章 分割と破壊──国連決議181とその衝撃 第4章 マスタープランの仕上げ 第5章 民族浄化の青写真──ダレット計画 第6章 まやかしの戦争と現実の戦争──1948年5月 第7章 浄化作戦の激化──1948年6月~9月 第8章 任務完了──1948年10月~1949年1月 第9章 占領、そしてその醜悪な諸相 第10章 ナクバの記憶を抹殺する 第11章 ナクバの否定と「和平プロセス」 第12章 要塞国家イスラエル エピローグ グリーンハウス 訳者あとがき 索引 著者プロフィール イラン・パペ (パペ イラン) (著) (Ilan Pappé) 1954年、イスラエル・ハイファ市生まれ。ハイファ大学講師を経て、現在、イギリス・エクセター大学教授、同大学パレスチナ研究所所長。イスラエル建国期のパレスチナ現代史を中心としたパレスチナ/イスラエル史研究。1984年に“Britain and the Arab-Israeli Conflict, 1948-1951”で博士号取得。主著に、The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947–1951 (I.B. Tauris, 1992) ; A History of Modern Palestine (Cambridge University Press, 2004) ; The Ethnic Cleansing of Palestine (Oneworld Publications, 2006=本書) などがある。近年は、ヨルダン川西岸地区・ガザ地区の被占領地、イスラエル国内のアラブ・パレスチナ人、アラブ世界出身のユダヤ教徒(アラブ系ユダヤ人)に関する著作も相次いで出版している。日本での講演録として、『イラン・パペ、パレスチナを語る』(つげ書房新社、2008年)がある。 田浪 亜央江 (タナミ アオエ) (訳) 広島市立大国際学部准教授。国際交流基金中東担当専門員、 成蹊大学アジア太平洋研究センター主任研究員などを経て、2017年4月より現職。専攻は中東地域研究、パレスチナ文化研究。単著に『〈不在者〉たちのイスラエル 占領文化とパレスチナ』(インパクト出版会、2008年)、最近の共著として『パレスチナを知るための60章』(明石書店、2016年)、『変革期イスラーム社会の宗教と紛争』(明石書店、2016年)、『中東と日本の針路 「安保法制」がもたらすもの』(大月書店、2016年)等があり、「ミーダーン〈対話のための広場〉」メンバーとしての共編書に『イラン・パペ、パレスチナを語る』(つげ書房新社、2008年)および『〈鏡〉としてのパレスチナ──ナクバから同時代を問う』(現代企画室、2010年)がある。 早尾 貴紀 (ハヤオ タカノリ) (訳) 1973年生まれ。現在、東京経済大学准教授。専攻は社会思想史。 単著に『ユダヤとイスラエルのあいだ』(青土社、2008年)、『国ってなんだろう?』(平凡社、2016年)、共編書に『シオニズムの解剖──現代ユダヤ世界におけるディアスポラとイスラエルの相克』(平凡社、2011年)、『ディアスポラから世界を読む──離散を架橋するために』(明石書店、2009年)、共訳書に、『イラン・パペ、パレスチナを語る』(つげ書房新社、2008年)、サラ・ロイ『ホロコーストからガザへ──パレスチナの政治経済学』(青土社、2009年)、ジョナサン・ボヤーリン/ダニエル・ボヤーリン『ディアスポラの力──ユダヤ文化の今日性をめぐる試論』(平凡社、2008年)、などがある。
-

スパイスとセーファースペース
¥770
SOLD OUT
スパイスを使ったチャイをみんなでつくって飲みながらセーファースペースについて考えるイベント「スパイスとセーファースペース」をまとめたzine。 本書の主な内容は、イベント後に行った座談会の内容をまとめたものです。新刊書店「本屋メガホン」を運営する和田、アーティスト・コレクティブ「ケルベロス・セオリー」のメンバーである山もと、デザインを担当する浦野のイベント企画者3人に加え、イベントに参加してくれた、東京都内のチェーン書店に勤める皆本夏樹さんと、東京都内で一箱本屋として活動する「Castellu」の店主の5名で、イベントを終えた感想やセーファースペースをめぐるそれぞれの実践、問題意識などについて話し合いました。 “イベントにおいて共通の問題意識として話し合われたのは、「セーファースペースについてまとまった資料や文献が少ない」ことでした。セーファースペースという概念そのものが、常により良い状態を模索し、そのあり方を更新し続けることを前提としているため、その都度立ち返ることのできる指針のようなものの存在は誰にとっても必要なはずだと考え、今回のイベントの様子をzineとしてまとめることにしました。本書が、これからセーファースペースについて考えたいと思っている人にとっての道標となったり、すでに実践している人にとってその考えを広げるような役割を果たすことができれば嬉しいです。”(「はじめに」より) *セーファースペースとは 「差別や抑圧、あるいはハラスメントや暴力といった問題を、可能な限り最小化するためのアイディアの 一つで、『より安全な空間』を作る試み」(『生きるためのフェミニズム パンとバラと反資本主義』堅田香緒里/タバブックス/2021年) のこと。様々なジェンダーや階級、言語やセクシュアリティを有する人々が一同に集まる社会運動の場において、そういった社会的背景の違いから生まれる差別や軋轢をいかに最小化するか、という問題意識から生まれたこの概念は、すべての人にとって完全に安全な空間など存在しないという前提を共有しつつ、それでも「“より安全な空間”を共同して作り続けていくこと」を目指す試みであることから、safeでもsafestでもなくsafer(=より安全な)という比較級が用いられています。 発行:本屋メガホン 編集:山もといとみ 浦野貴識 印刷:when press https://www.whenpress.com 判型:W105mm×H250mm 12ページ
-
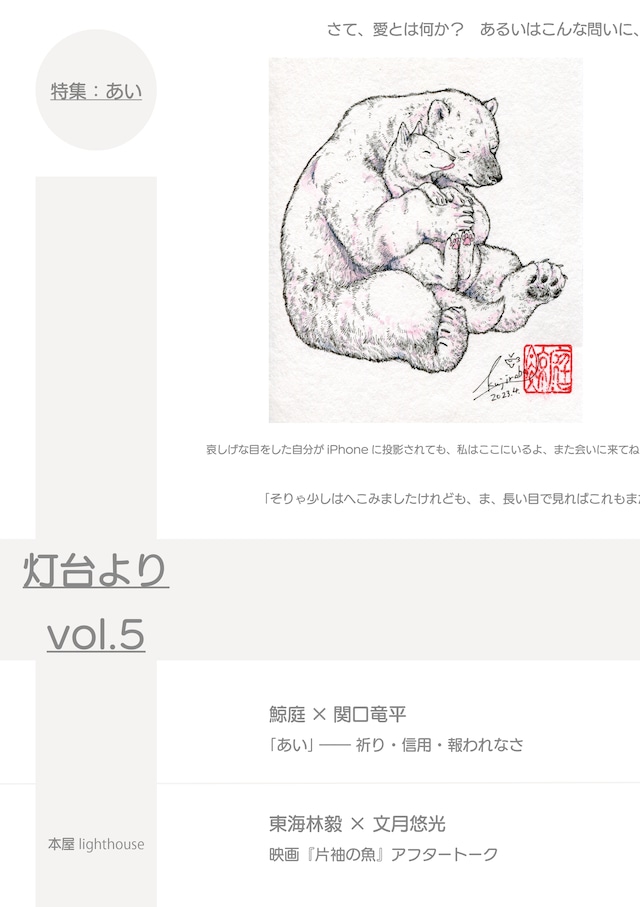
灯台より vol.5 特集:あい
¥1,320
SOLD OUT
特集:あい 本屋lighthouseが定期的に刊行しようと思いつつも不定期に刊行している文芸誌的なサムシング、『灯台より』のvol.5です。 今号より大増量でお送りします。 気分的には第2期的な感じです。 *PDF版も刊行しています 目次 鹿子裕文 p2 「真っ赤な夜のブルース」 #5 損してナンボのイマジン 橋本亮二 p6 「本を抱えて会いにいく」 #5 あいを受けとる 僕のマリ p12 「まほろばハイウェイ」 #3 空前のゾウブーム 対談 p16 鯨庭×関口竜平 「あい」 ―― 祈り・信用・報われなさ 梶本時代 p42 「梶本時代の人生あじゃぱ節」 #5 恥の海より エッセイ p48 ひらいめぐみ 曖昧 エッセイ p52 小原 晩 あの他人 対談 p54 東海林毅×文月悠光 映画『片袖の魚』アフタートーク ルポ p78 中村佳太 パートナーシップ制度の導入を求める陳情が逆転採択されるまでの経緯。 とそこで気づいた問題点。 エッセイ p90 水上 文 ジャンピング・あい エッセイ p96 小澤みゆき ポケモンLEGENDSアルセウスのかんそう 守屋 信 p102 「十九年」 #5 ゆっくりおやすみ、また明日ね 編集後記:灯台守の日誌 p112 「現代 未刊のプロジェクト」 #5 *休載 本間 悠 「書店員です。兼業酒婦です。」 仲西森奈 連載小説 「どこに行ってもたどり着く場所」 仕様 A5版・116p フルカラー 表紙イラスト:鯨庭 刊行日:2023年7月10日
-

ユートピアとしての本屋 暗闇のなかの確かな場所
¥1,870
SOLD OUT
*おぺんのらくがきをご希望のかたは備考欄にてその旨お知らせください\(•ө•)/ 以下、出版社作成の紹介文です。なんか恥ずかしい。 ---------------------------------------------------------------------------------- たった一人で独立書店を立ち上げ、反差別をかかげた果敢な発言でも注目される「本屋lighthouse」の若き店主による単著。知への信頼が揺らぐ時代に、誰もが生きられる空間をつくるための実践と思考の書。 [目次] はじめに 1 本屋になるまでの話 2 メディア/クリエイターとしての本屋 3 ひとりの人間としての本屋 4 本屋にとっての反ヘイト・反差別とは 5 差別は道徳では解決しない 6 出版業界もまた差別/支配構造の中にある 7 セーファースペースとしての本屋 8 教室としての本屋 9 ユートピアとしての本屋 おわりに Kindle→https://amzn.to/3LhD8tD
-

おぺん選書便(3冊/5500円くらいのやつ)
¥5,500
SOLD OUT
本3冊+lighthouseロゴトートバッグ1つのセットです。 本3冊でだいたい5500円(税込)くらいになるように選書します。 設定金額に届かない分をトートバッグで吸収するスタイルです(トートバッグ単体は1000円+税で販売中)。 備考欄に ・トートバッグの色(ナチュラル/ネイビー) ・読みたいジャンルやテーマ(3つまで) ・くわえてNGのジャンルやテーマ、作家などがあれば(これは読みたくない!というものを知れたほうがありがいもので……) ・そのほか細かい希望があれば遠慮なくどうぞ あたりをご記入ください。 この本は入れてくれ、という「注文」もなんなりと。 そのほか質問などあればお問い合わせくださいませ。 *1万円選書のサービス「ブックカルテ」にも参加していますので、そちらのご利用も大歓迎です https://bookkarte.com

-

ゆさぶるカルチュラル・スタディーズ
¥2,530
SOLD OUT
コギャル、都会と地方、モバイルメディア、F1、音楽、フェミニズム、漫画、ボディ・プロジェクト、社会運動、アート等、多様な文化の側面から逆なでに読み解くカルチュラル・スタディーズ入門。またカルチュラル・スタディーズとはなにか? 今までのカルチュラル・スタディーズの軌跡を概観しつつ、これからの課題についても示唆した意欲作。 目次 第1章 モバイルメディアの殻・繭・棘(ケイン樹里安) 第1節 殻と繭 第2節 監視vsチル 第3節 棘 第4節 夢と悪夢のスマートシティ 第5節 全力と諦念 研究コトハジメ:深夜のマクド 第2章 「ここ」ではない「どこか」へ:都会と田舎をめぐる若者の物語を移動/越境から考える(清水友理子) 第1節 移動は「田舎から都会へ」から「都会から田舎へ」へ? 第2節 どこへでも行ける?フラット化=ポスト・アーバン化する社会 第3節 さらに遠くへ、あるいは、ずっと地元のままで? 第4節 「田舎vs都会」を超えて 研究コトハジメ:フィールドに出る一歩手前の準備:五感を働かせる 第3章 奪い・奪われ・奪い返すスタイル:サブカルチャーとしてコギャルを読み解く(関根麻里恵) 第1節 サブカルチャーとは何か 第2節 コギャルというサブカルチャー 第3節 スタイルをめぐる闘争と交渉 第4節 進化する(コ)ギャルスタイル 研究コトハジメ:『GALS!』が教えてくれたこと:フィクション作品が与えた影響について 第4章 フレンチポップのなかのジェンダー構造:ラブソングにおける対抗的実践を読みとる(中條千晴) 第1節 フレンチポップのラブソングに見る男女の関係性 第2節 現代フランスとフェミニズム 第3節 アンジェルの『Balance ton quoi』に見る実践 第4節 結論(づけないために) 研究コトハジメ:ポピュラー音楽を分析する 第5章 レズビアンの剥片化に抗して:『作りたい女と食べたい女』を読む(竹田恵子) 第1節 セクシュアル・マイノリティの存在・アイデンティティ・権利 第2節 ポルノ、そして「百合」から「レズビアン」の表象へ 第3節 「レズビアン」存在の剥片化に抗して 研究コトハジメ:「自分のありかたを発明する」 第6章 スポーツのファンダム:クルマ文化とF1(加藤昌弘) 第1節 参加型文化としてのF1のファンダムを捉え直す 第2節 F1と映像メディア 第3節 グローバルなスポーツはナショナリズムを変えるのか 第4節 グローバル資本主義と格差の問題 第5節 女性とF1のかかわり方 第6節 F1を「見る」ことと「遊ぶ」こと 研究コトハジメ:「好き」を仕事(研究)にすべきか 第7章 創られる理想、作られる身体:私たちはどのようにボディ・プロジェクトへと向かうのか(竹﨑一真) 第1節 身体をどうとらえるか? 第2節 ポスト工業社会と身体の理想 第3節 コンフィデンス・カルチャーとしてのボディ・プロジェクト 第4節 身体から社会をゆさぶる 研究コトハジメ:記号であり生モノでもある筋肉 第8章 「黒い暴動」:移民たちはなぜ踊り始めたのか(稲垣健志) 第1節 奴隷たちの隠れた抵抗 第2節 「ロンドンは僕のための場所」か?:イギリスにおけるレイシズム 第3節 カーニヴァルを再創造する 第4節 「危機」を取り締まる 研究コトハジメ:「真似る」という文化実践 第9章 『三つ目がとおる』と失われた過去の〈場所〉マヤ文明(鋤柄史子) 第1節 二つの表象:三つ目とマヤ文明 第2節 マヤ文明表象とポストコロニアリズム 第3節 戦後日本のオカルトカルチャーと手塚のジレンマ 研究コトハジメ:ゆさぶる「目」を身につける 第10章 オンライン空間の文化と社会参加:韓国におけるウトロ地区支援の一端(全ウンフィ) 第1節 オンライン空間に浮かび上がる「社会」 第2節 文化を基盤とする社会空間 第3節 遊びの空間を橋渡しする人々 第4節 サブカルチャーの空間性からみる社会参加 研究コトハジメ:場所に込められたもの・こと 第11章 人と歴史をつなげる現代アート:現代在日コリアン美術を例に(山本浩貴) 第1節 現代アートとは何か 第2節 ソーシャリー・エンゲージド・アート 第3節 リレーショナル・アートと敵対 第4節 現代在日コリアン美術:呉夏枝と琴仙姫 第5節 現代アートの力と可能性 研究コトハジメ:現代アートを「研究」する 第12章 文化の「遺産化・財化」に抗う文化実践:「内灘闘争――風と砂の記憶――」展をめぐって(稲垣健志) 第1節 内灘闘争 第2節 文化を「遺産化・財化」するということ 第3節 「風と砂の記憶」展2018・2021 第4節 それがアートである理由 研究コトハジメ:ぶらぶらのススメ 第13章 「カルスタ」を逆なでに読む:カルチュラル・スタディーズをゆさぶるために(稲垣健志) 第1節 カルスタの「誕生」 第2節 カルチュラル・スタディーズの翻訳:カルスタはパンクに出会ったのか? 第3節 カルチュラル・タイフーンの発生:台風はどこに上陸するのか? 第4節 カルスタをどう逆なでるか 研究コトハジメ:それでもやはり 著者プロフィール 稲垣 健志 (イナガキ ケンジ) (著/文 | 編集) 金沢美術工芸大学美術工学部准教授。 主著(論文)に、‘Radicals Strike Back: A Memorandum for the Cultural Studies of Black Radicalism in Britain’『金沢美術工芸大学紀要』第65 号(2021 年)、「カルチュラル・スタディーズを裏 返す―A. シヴァナンダンをめぐるいくつかの断章」『年報カルチュラル・スタディーズ』Vol. 10(2022 年)など。訳書に、ガルギ・バ タチャーリャ『レイシャル・キャピタリズムを再考する―再生産と生存に関する諸問題―』(人文書院、2023 年)。
-

戦争語彙集
¥2,200
SOLD OUT
「わたしの家も、この街も、置いていけばゴミになるの?」 「ゴミ」「星」「林檎」……戦争の体験は人が言葉に抱く意味を変えてしまった。ウクライナを代表する詩人が避難者の証言を聴き取り、77の単語と物語で構成した文芸ドキュメント。ロバート キャンベルが現地を訪ねて思索した手記とともに、自ら翻訳して紹介。 目次 旅立ちの前に ロバートキャンベル 戦争語彙集――オスタップ・スリヴィンスキー作/ロバートキャンベル訳 序 バス スモモの木 おばあちゃん 痛み 稲妻 妊娠 バスタブ 熊 結婚式 通り キノコ 雷 呼出音 「遠い」と「近い」 我が家 シャワー 住宅 生 土 星 歯 身の上話 食べもの ココア カレンダー カナリア アヒルの子 入場券 部屋 猫 鍵 色彩 お馬さん 恋愛 きれいなもの チョーク 血 銃弾 ランプ 手紙 愛 マドレーヌ 焼き網 都会 お祈り 空 ニュース 脚 ナンバープレート 洞窟 地下室 プラハ お別れ ラジオ 悦び 魚 自由 倉庫 ゴミ 夢 スイーツ 太陽 歌 記事 立て看板 禁句 戦車 動物 テトリス 沈黙 身体 パン生地 ケーキ 遺体 しっぽ 数 林檎 戦争のなかの言葉への旅――ロバートキャンベル 一 列車から、プラットフォームに降り立つ――行き交う人々と言葉 二 人形劇場の舞台袖で、身をすくめる――言葉の意味が変わるとき 三 階段教室で、文学をめぐる話を聞く――断片としての言葉 四 ブチャの団地で、屋上から見えたもの――引き裂かれたランドスケープ 五 シェルターのなか、日々をおくる――とどまる空間で、結び合う人々 六 あかるい部屋で、壁に立てかけられた絵を見る――破壊と花作り 環のまわるが如く ロバートキャンベル 「戦争語彙集」原書謝辞 Kindle→https://amzn.to/3tzY0X3
-

かわいいピンクの竜になる
¥2,090
SOLD OUT
大人気連載、ついに書籍化 ロリィタ、お姫様、妖精のドレス、少年装、幻獣のような髪、メイク…… 世界と人間に絶望した著者が、ロリィタと出会い「自分らしく装う」ことに目覚めて、本来の姿を取り戻すまで。 気鋭の歌人・小説家、川野芽生が「装いと解放」を綴る、初のエッセイ集。 それほどにその服は私に——私の姿かたちだけでなく、私の精神に——しっくりと馴染んでいた。 あるべき世界では、私はずっとこんな服を着て生きてきたに違いない。間違ったこの世界で、それでも私はようやく、自分の羽衣を取り戻した。 「#1 少女は従わない」より 目次 #1 少女は従わない #2 姫は番わない #3 人形は頷かない #4 少年は留まらない #5 ミューズはここにいない #6 魔女は終わらない #7 エルフは眠らない #8 妖精に身体はない #9 幻獣は滅びない #10 天使は汚れない #11 ドリュアスは眼に視えない おわりに 著者 川野芽生 (カワノ・メグミ) 小説家・歌人・文学研究者。第29回歌壇賞受賞。第一歌集『Lilith』(書肆侃侃房、2020年)にて第65回現代歌人協会賞受賞。小説集に『無垢なる花たちのためのユートピア』(東京創元社、2022年)と『月面文字翻刻一例』(書肆侃侃房、2022年)、長編小説に『奇病庭園』(文藝春秋、2023年)がある。
-

Q&A多様な性・トランスジェンダー・包括的性教育 バッシングに立ちむかう74問
¥1,870
SOLD OUT
トランス差別言説に対抗し、性教育の指針を示す トランス排除を煽るネット上のデマや誤解、陰謀論をファクトに基づき検証。LGBTQへの差別や恐怖を利用し包括的性教育を攻撃する右派のバックラッシュを許さないために、当事者・専門家らが結集したコンパクトなQ&A集。 [目次] はじめに 1章 LGBTQとは? トランスジェンダーとは? Q01 LGBTQとは何ですか? Q02 トランスジェンダーと同性愛はどう違いますか。 Q03 トランスジェンダーはどれくらいの割合で存在しますか? Q04 LGBTQをめぐってどんな差別やいじめ、ハラスメントがありますか。 Q05 LGBTQの人は学校や職場で何に困っていますか。 Q06 性的指向や性自認は治せるのですか? Q07 日本は昔からLGBTQについて寛容だったから、差別はないのではないですか。 Q08 学校でのLGBTQ教育はどんな内容ですか。過激な内容ですか。 Q09 同性婚を認めると、少子化や伝統的家族観の崩壊につながりませんか。 Q10 戸籍を変更しているトランスジェンダーの人はどれくらいいますか。 Q11 性同一性障害は病気ではないのですか。トランスジェンダーとはどう違うのですか? Q12 性同一性障害は病気ではなくなるのですか。 Q13 トランスジェンダーの人たちは脱病理化を求めているのですか? Q14 何歳くらいからトランスジェンダーと気づきますか。 Q15 トランスジェンダーにはどのような人が含まれますか。国連の定義では異性装をする人も含まれるのですか? Q16 興奮するために女装をする男性もトランス女性には含まれますか? Q17 トランスジェンダーの人はどのように性別を変えるのですか。 Q18 生まれ持った性別を変えることは、不幸な生き方ではないでしょうか。 Q19 トランス女性は、お化粧やスカートが好きな男性として生きればよいのではないでしょうか。 Q20 手術をして、ペニスを除去してから女性と認めるべきではないでしょうか。 Q21 男とか女とか関係なく、その人らしく生きればいいのでは? どうして性別を変えようとするのでしょうか。 [コラム]ニュースから読み解く 最近のLGBTQをめぐる社会の変化 2章 トランスジェンダーをめぐるバッシングのウソ・ホント Q01 デマによるバッシングが激化しているのでしょうか。 Q02 トランスジェンダーに対するバッシングはなぜ激化しているのでしょうか? Q03 トランスジェンダーの人はどのトイレを使うのでしょうか。「だれでもトイレ」を使えばいいのではないでしょうか? Q04 トイレや更衣室の利用は法律上の性別に限定すべきではないでしょうか? 法的な性別と異なるトイレや更衣室を使うのは犯罪ではないでしょうか。 Q05 公衆浴場はトランスジェンダーの人をどう扱っていますか。 Q06 トランスジェンダーの権利を認めると性犯罪が増えるのではないですか。 Q07 自治体のLGBT差別禁止条例の制定によって、男性が女性用トイレや公衆浴場に入れるようになっているのでしょうか。 Q08 2023年に成立したLGBT理解増進法はどんな法律でしょうか。この法律によって男女別施設の利用基準が変わってしまうのでしょうか。 Q09 施設を男女別に分けることは差別になるのでしょうか。 Q10 「差別」の定義があいまいなままLGBTへの差別を法律で禁止すると、、訴訟が乱発されて社会が分断されるおそれがあるのではないですか。 Q11 心は女性だという人が女性用トイレや女湯を利用するのを拒否したら、裁判になり法律で罰せられるのでしょうか。 Q12 LGBT理解増進法によって女性用トイレがなくなり、すべてのトイレが男女共用になってしまうのでしょうか。公園ではなぜ女性トイレが減っているのですか。 Q13 選挙の候補者をはじめとする「女性向け枠」について、トランスジェンダー女性との関係性をどう考えたらよいでしょうか。「男性」によって女性枠が奪われてしまうのではないですか。 Q14 トランスジェンダー女性による女性スポーツ参加をどう考えたらよいでしょうか。 Q15 刑務所などの収容施設におけるトランスジェンダーの扱いはどうなっていますか。 Q16 セルフIDとはなんでしょうか。日本の性同一性障害特例法はなぜ改正が求められて Q17 トランスジェンダーの権利擁護をする人は、女性の性暴力被害に無関心ではないでしょうか。 Q18 性別を変える治療をして後悔する人が多いと聞きましたが、本当でしょうか。 Q19 製薬会社が儲けるためにトランスジェンダーを増やそうとしているって本当でしょうか。 Q20 子どものころに後戻りできない治療をおこなうことは不適切ではないでしょうか。 Q21 LGBTQの権利を認めると、小児性愛などを認めることにつながりますか。 Q22 LGBTQは「文化共産主義」で、社会の「性秩序を崩壊させる」思想なのでしょうか? Q23 性暴力被害者を支援する立場からトランスジェンダーバッシングに反対する人もいるのですか。 [コラム]LGBTQグルーミング陰謀論にご注意! 3章 日本の子ども・若者の性はどんな現状にあるの? Q01 性にかかわる人権とはどういうことですか。日本ではどのような現状や課題があるのでしょうか。 Q02 日本の若者の性の現状と課題として、どのようなことがありますか。 Q03 子ども・若者の権利と性教育はどのようにつながっているのですか。 Q04 自分の性のあり方に悩む子ども・若者は日本にどのくらいいて、どんな悩みがあるのでしょうか。 Q05 性的同意についての理解は日本でどのくらい広がっていますか。 Q06 子どもや若者が性について相談したいとき、どのような相談先がありますか。 Q07 子ども・若者への性暴力の理解や支援で重要なことはなんでしょうか。 Q08 性の多様性・包括的性教育バッシングについて、若者はどのように受けとめているのですか。 Q09 若い人たちが相談・支援を受けやすい工夫として、どのようなことが考えられますか。 Q10 性の多様性や包括的性教育について学んだり、活動に参加したりするには、どのような場がありますか。 [コラム]性教育・性の健康と権利にまつわる施策に若者がかかわる意義とは 4章 包括的性教育って、どんな性教育なの? Q01 包括的性教育の「包括的」とはどういうことですか。普通の性教育とは違うのですか? Q02 包括的性教育とは、何をめざす教育なのですか。 Q03 包括的性教育はいつごろからはじまり、どんな国でおこなわれているのですか。 Q04 包括的性教育は日本ではおこなわれているのですか。学習指導要領との関係はどうですか。 Q05 包括的性教育は、子どもたちに性自認の混乱をもたらし、10代の性交渉や性感染症の増加を引き起こしているというネット記事を読みましたが本当ですか。 Q06 アメリカでは包括的性教育を禁じている州もあると聞きました。どういう理由なのですか。 Q07 10代のセックスを遅らせるには、包括的性教育よりも「性的自己抑制教育」のほうが効果的というのは本当ですか。 Q08 現在、特別支援学校や特別支援学級で、障害児を対象にした性教育はどのような方針に基づいて実施されているのでしょうか。包括的性教育はおこなわれているのでしょうか。 Q09 日本で包括的性教育を推進している団体にはどのようなものがありますか。 Q10 学校の教員自身が性教育を受けた経験がありません。このような状態で幅広い知識が必要な包括的性教育が実践できるとは思えません。どうしたら実践できるでしょうか。 [コラム]包括的性教育がもたらす変化と展望──大東学園高校の経験から 5章 世界の流れと日本の動き、これからの課題 Q01 国連における多様性の尊重と包括的性教育推進の活動はどのような内容でしょうか。 Q02 アメリカでも性教育をめぐって分断や対立があるそうですが、最近の動きにはどのような特徴がありますか。 Q03 北欧の国々では、セクシュアリティをめぐる政策にどのような具体的な動きがあるのでしょうか。 Q04 ジェンダー平等をすすめている国、停滞している国をジェンダー・ギャップ指数で比較すると、どのような推移と現状にあるのでしょうか。 Q05 避妊・中絶・性感染症などの「性と生殖の健康と権利」保障に関する国際的動向と日本の現実にはどのようなちがいがあるのでしょうか。 Q06 日本における性教育・ジェンダー教育にかかわる法律や条例にはどのような内容のものがあるのでしょうか。 Q07 現在のトランスジェンダーバッシング、包括的性教育バッシングに、統一協会などの宗教右派や右派団体などはどのようにかかわっているのでしょうか。 Q08 日本において子どもや保護者が性教育に何を望んでいるのかについての調査はありますか。あればその内容を紹介してください。 Q09 包括的性教育をすすめていくうえで、学校内での合意づくりや保護者、性教育に関連する団体、地域社会との連携・共同について、どのような点に留意したらよいでしょうか。 Q10 包括的性教育を日本でも広く学校教育や学校外教育に根づかせていくには、どのようなことに取り組む必要があるでしょうか。 相談先一覧 Kindle→https://amzn.to/479TlZF
-

分断されないフェミニズム ほどほどに、誰かとつながり、生き延びる
¥2,640
SOLD OUT
非婚/未婚/既婚、正規労働/非正規労働、性差別的な売春か/セックスワークか、女性の保護か/男女平等か――。フェミニズムは分断と連帯にどう向き合えばいいのか。 フェミニズムの議論を骨格に、現場の声にふれた経験に基づき、女性たちが簡単にはつながれない現実を見据えたうえで、シスターフッドとは何かを問いかける。 女性たちが差別に抗い、不満に共感しあいながらも、ともに声を上げられない現実を、ジェンダーに基づく権力構造による分断だけではなく、考え方や生き方、事情や立場が異なる個人の関係性などの視点から読み解く。 「分断」を乗り越えることを模索し、「ほどほどに、誰かとつながり、生き延びる」ための女性のこれからを提案して、長年のフェミニズムの場での活動と思索に基づいて女性のつながりのあり方の再考を求める評論。 目次 はじめに――オンナの呪いを解く 第1章 女は連帯できないのか――フェミニズムとシスターフッド 1 呪いを解く知としてのフェミニズム 2 フェミニズムが見据えてきた「女同士」 3 シスターフッドの発見――分断のメカニズムへの抵抗として 第2章 対話、問い直し、フェミニズム 1 女性の活動への関心と縁 2 平場という関係とその困難 3 「対話」の工夫と調整 4 他者との対話、自己との対話 第3章 フェミニズムの「呪い」と女の欲望 1 フェミニストとしての自分を縛る「呪い」 2 ロック文化とフェミニズム 3 「エロ」はフェミニズムの敵なのか 4 「酒場女子」をめぐるモヤモヤ 5 フェミニズムか反フェミニズムかの二分法を超えて おわりに――他者と適度につながり続けるために 著者プロフィール 荒木 菜穂 (アラキ ナホ) (著) 1977年、三重県生まれ。関西大学ほか非常勤講師、大阪公立大学客員研究員。日本女性学研究会、日本女性学会、ウィメンズアクションネットワークなどで活動。共著に『やわらかいフェミニズム――シスターフッドは今』(三一書房)、『巨大ロボットの社会学――戦後日本が生んだ想像力のゆくえ』(法律文化社)、『ポスト〈カワイイ〉の文化社会学――女子たちの「新たな楽しみ」を探る』(ミネルヴァ書房)、論文に「現代日本のジェンダー・セクシュアリティをめぐる状況とこれからのフェミニズムについて考える――菊地夏野『日本のポストフェミニズム:女子力とネオリベラリズム』を読んで」(「女性学年報」第40号)など。 Kindle→https://amzn.to/487LVrj
-

彼女たちのまなざし 日本映画の女性作家
¥2,640
SOLD OUT
女性映画作家たちのまなざしからよみとく日本映画の最前線。 “「映画監督」と呼ばれる人々が一人残らず女性であったなら、当然そこに「女性監督」という呼称は生まれえない。かつて映画監督には、男性しかいないとされていた時代があった。”(「序論」より) そのような時代は果たして本当の意味で「過去」となりえているのだろうか? 本書は、この問題提起を出発点として、日本映画における女性作家の功績を正当に取り上げ、歴史的な視座を交えながらその系譜をたどり、彼女たちのまなざしから日本映画の過去・現在・未来を読み替えていくことを試みる、これまでにない映画批評である。 対象をあえて女性のみに限定し、大勢の男性作家たちのなかにいる数少ない女性作家という図式をまずはいったん解体することから始めるというアプローチから、これまでの日本映画の歴史にひそむ性の不平等や権力の不均衡の問題にせまり、日本映画史の捉え直しを通して、新しい地図を描き出す。 伝統的な家父長制から脱却し、多様な属性とオルタナティヴな関係性を個々人が模索する2020年代以降の時代精神から読みとく、日本映画の最前線。 取り上げる主な作家 西川美和、荻上直子、タナダユキ、河瀨直美、三島有紀子、山田尚子、瀬田なつき、蜷川実花、山戸結希、中川奈月、大九明子、小森はるか、清原惟、風間志織、浜野佐知、田中絹代……ほか多数 論考から作品ガイドまで、全原稿書き下ろし 作家ごとの評論だけでなく、日本映画史における女性監督の系譜、次世代の新進作家紹介、今見るべき日本の女性監督作品の100本ガイドまで。作家論、歴史、状況論、作品ガイドまでを網羅した、著者渾身の書き下ろし。 === ◎目次 序論 児玉美月 第1章 日本映画における女性監督の歴史 北村匡平 1 女性監督のパイオニア/2 胎動期──1950〜1980年代/3 黎明期──1990年代/4 ニューウェーヴ──2000年代/5 黄金期──2010年代以降 第2章 16人の作家が照らす映画の現在地 北村匡平+児玉美月 1 西川美和論──虚実、あるいは人間の多面性 2 荻上直子論──「癒し系」に「波紋」を起こすまで 3 タナダユキ論──重力に抗う軽やかさ 4 河瀨直美論──喪失と再生を描く私映画 5 三島有紀子論──陰翳の閉塞空間とスクリーン 6 山田尚子論──彼女たちの空気感と日常性 7 瀬田なつき論──どこにもない「時間」を生きる 8 蜷川実花論──恋と革命に捧げられた虚構の色彩 9 山戸結希論──すべての「女の子」たちへ 10 中川奈月論──世界の崩壊/解放と階段のサスペンス 11 大九明子論──意外と「だいじょうぶ」な女たち 12 小森はるか論──記録運動としての積層と霊媒 13 清原惟論──マルチバースで交感する女性身体 14 風間志織論──日常の細部を照らし出すフィルム 15 浜野佐知論──男根的要請とフェミニズム的欲望の闘争 16 田中絹代論──欲望する身体とセクシュアリティ 第3章 次世代の作家たち 児玉美月 「映画」が孕む暴力性への自覚/日本の社会問題と向き合う/独自の作家性を貫く/学園映画の異性愛規範に抗する/オルタナティヴな関係性を模索する/新たな属性を可視化させる/まだ見ぬ未来へのシスターフッド 〈付録〉女性映画作家作品ガイド100 児玉美月+北村匡平 あとがき 北村匡平 著者について 北村匡平(きたむら・きょうへい) 映画研究者/批評家。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授。単著に『椎名林檎論——乱調の音楽』(文藝春秋、2022年)、『アクター・ジェンダー・イメージズ——転覆の身振り』(青土社、2021年)、『24フレームの映画学——映像表現を解体する』(晃洋書房、2021年)、『美と破壊の女優 京マチ子』(筑摩書房、2019年)、『スター女優の文化社会学——戦後日本が欲望した聖女と魔女』(作品社、2017年)、共編著に『川島雄三は二度生まれる』(水声社、2018年)、『リメイク映画の創造力』(水声社、2017年)、翻訳書にポール・アンドラ『黒澤明の羅生門——フィルムに籠めた告白と鎮魂』(新潮社、2019年)などがある。 児玉美月(こだま・みづき) 映画文筆家。共著に『反=恋愛映画論——『花束みたいな恋をした』からホン・サンスまで』(ele-king books、2022年)、『「百合映画」完全ガイド』(星海社新書、2020年)、分担執筆に『ロウ・イエ 作家主義』(A PEOPLE、2023年)、『デヴィッド・クローネンバーグ 進化と倒錯のメタフィジックス』(ele-king books、2023年)、『フィルムメーカーズ24 ホン・サンス』(宮帯出版社、2023年)、『ジャン=リュック・ゴダールの革命』(ele-king books、2023年)、『韓国女性映画 わたしたちの物語』(河出書房新社、2022年)、『アニエス・ヴァルダ——愛と記憶のシネアスト (ドキュメンタリー叢書)』(neoneo編集室、2021年)、『岩井俊二 『Love Letter』から『ラストレター』、そして『チィファの手紙』へ』(河出書房新社、2020年)、『フィルムメーカーズ21 ジャン=リュック・ゴダール』(宮帯出版社、2020年)など多数。『朝日新聞』、『キネマ旬報』、『文藝』、『ユリイカ』、『文學界』などに寄稿。
-

マリはすてきじゃない魔女
¥1,320
SOLD OUT
だれかのための「すてき」はもういらない。 自分の心に素直になれば、あなたも「魔女」になれるかも!? ふたりの魔女ママとくらす11歳の魔女マリは、食いしんぼうで、おしゃれが大好きな女の子。「魔法は自分のために使ってはいけない」きまりを今日も忘れ、ジャムドーナツを「倍数の魔法」で巨大化させたから学校じゅうが大パニック! 親友ふたり、算数が得意なスジと魔女に憧れるレイのおかげで無事だったのに、ママからはお説教。大人たちは、みんなと生きるためには、人の役に立つ「すてきな魔女」になりなさいっていうんだけど、それってなんかヘンじゃない……? 『本屋さんのダイアナ』『らんたん』の柚木麻子、初の児童文学! マリにふりまわされながらも、町のみんなが自分のための魔法を見つけていく物語。小学中学年から大人まで/総ルビ/挿絵入り。 【推薦コメント】 なんという、ズバリ核心をついた題名! そう、魔女って「すてき」なものじゃないんです。魔女になるとはつまり野性を呼び起こし「我がまま」(私のまま)になるってこと。肝心かなめのアドバイスが全部入りのこの本は、間違いなく未来の魔女たちの必読書&すべての女の子たちのお守りとなるはず。ぜったい娘に読ませます! ーー谷崎榴美(現代魔女) 魔法があり、女のひと同士で結婚でき、トランスジェンダーの子が普通に暮らす、そんな夢のような世界にも差別はあって……。「すてきな魔女」からこぼれ落ちる女の子たちのキュートな活躍に、読んでいて元気が出ます。よくあるトランスジェンダー物語に飽きているひとにもおすすめ! ーー三木那由他(言語哲学者) 目次 第1章 ドーナツパニック 第2章 魔女の歴史 第3章 コウモリパフェ 第4章 南極と南国 第5章 グウェンダリンの秘密 第6章 すてきの代償 第7章 魔法だけが魔法じゃない 第8章 きょうはみんなの記念日 作者あとがき 著者プロフィール 柚木麻子 (ユズキ アサコ) (著/文) 1981年生まれ。大学を卒業したあと、お菓子をつくる会社で働きながら、小説を書きはじめる。2008年に「フォーゲットミー、ノットブルー」でオール讀物新人賞を受賞してデビュー。以後、女性同士の友情や関係性をテーマにした作品を書きつづける。2015年『ナイルパーチの女子会』で山本周五郎賞と、高校生が選ぶ高校生直木賞を受賞。ほかの小説に、「ランチのアッコちゃん」シリーズ(双葉文庫)、『本屋さんのダイアナ』『BUTTER』(どちらも新潮文庫)、『らんたん』(小学館)など。エッセイに『とりあえずお湯わかせ』(NHK出版)など。本書がはじめての児童小説。 坂口友佳子 (サカグチ ユカコ) (イラスト) 大阪府出身。京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)キャラクターデザイン学科卒業。TIS会員。はじめての将来の夢は、人魚か魔女になること。大好きなファンタジーの世界に浸れることから、絵を描くのが大好きになる。現在は、イラストレーターとして活動し、絵本や児童文学の表紙や挿絵、お菓子のパッケージや広告などの絵を手がける。絵本に、自身の飼っている白猫をモデルにした『どこどこ けだまちゃん』(ひるねこBOOKS)がある。
-

雨がしないこと 上下巻セット
¥1,760
SOLD OUT
「雨ちゃんは、話の合わない、私のともだち」 私たちが雨ちゃんについて知っていること。 突然、郊外の古くて小さな平屋に引っ越したこと。 凝り始めると同じ料理ばかりを作り続けること。 そしてーー雨ちゃんは、恋をしない。 みんなとちょっと違うけど、変わっているのはみんなと同じ。 第26回手塚治虫文化賞【短編賞】受賞作家が贈る、「恋をしない」花山雨(30)を巡る群像物語。 Kindle(上巻)→https://amzn.to/3TA0saA Kindle(下巻)→https://amzn.to/3TIZ0Tg
-

イエルバブエナ
¥1,375
SOLD OUT
原題:Yerba Buena その香りが、その空間が、そのひとときが、わたしを癒してくれる。 傷ついても、過去に囚われても──── サラは衝撃的な別れをきっかけに、16歳で家から逃げ出した。 向かった先はロサンゼルス。懸命に自立を目指し、数年後に人気のバーテンダーとなった。 エミリーは将来のプランが定まらず、自信が持てない大学生。 フラワーアレンジメントの仕事で訪れたレストラン<イエルバブエナ>で、 バーテンダーたちにカクテルの作り方を教えていたサラと出会う。 ふたりは惹かれ合うが、トラウマや家族のしがらみ、喪失の記憶に囚われてしまう。 心の傷と向き合い、前に進むために必要なものは何か。 もがきながら自分の道を見つけるふたりの女性のラブストーリー。 【レビュー】 作り込まれたカクテルのように、さまざまな香りがじわじわと花ひらく……あらゆる感覚に訴えかける、細部まで色鮮やかなごちそうだ。・・・・・・ラクールの技がまぶしい・・・・・・ほろ苦さ、しょっぱさ、甘さが一気に押し寄せる。 ――ニューヨークタイムズ・ブックレビュー 『イエルバブエナ』は、現代の複雑な愛についての考察である……サラとエミリーを苦しめるトラウマ、そして彼女たちの希望と回復が、穏やかで優しさに満ちた目で観察され、静かな散文に見事に表現されている……登場人物が魅力的な美しいフィクションだ。完璧なカクテルのように、飲み終わった後もずっと、記憶に残るだろう。 ――サンフランシスコ・クロニクル 『イエルバブエナ』はご褒美のようで慎ましく、親密なのにとらえどころがない、これらが完璧に調和し素敵な香りが漂います。ミステリアスで魅力的なだれかがミックスした、見事なカクテルのよう。大切な作品です。 ――ケイシー・マクイストン ニューヨーク・タイムズ・ベストセラー小説『One Last Stop』、『赤と白とロイヤルブルー』著者 あなたの心が抱える真実と、あなた自身を守るための嘘。あなたを築いた道と、あなた自身が築く道。立ち止まることと、修復すること。本書はこれらのことが描かれた、極上の物語です。ニナ・ラクールは、彼女にしかできないやり方で、心を満足させ、感動的で、ずっと記憶に残るラブレターを書いたのです。人生のあらゆる“はじまり”へのラブレター。ほんとうに美しい。 ――コートニー・サマーズ ニューヨークタイムズ・ベストセラー小説『Sadie』、『ローンガール・ハードボイルド』著者 ■著者 ニナ・ラクール Nina LaCour マイケル・L・プリンツ賞などの受賞歴のあるベストセラー作家。 『WE ARE OKAY』などヤングアダルト小説を発表(すべて未邦訳)。 本作は著者初の大人向けの作品である。サンフランシスコに妻と娘と暮らす。 ■訳者プロフィール 吉田育未(よしだ・いくみ) 英日翻訳者。 エマ・ドナヒュー『星のせいにして』(河出書房新社)、『聖なる証』(オークラ出版)、 絵本『ちいさなあおいトラックのリトルブルー』シリーズなど訳書多数。 佐賀県出身。トロント大学修士。 引っ越しが多く、原作初読時は東京、 翻訳作業中はカナダアルバータ州、刊行時は香港に暮らす。
-

『ベイブ』論、あるいは「父」についての序論
¥1,200
SOLD OUT
著:柿内正午 幼少期に自身を魅了した映画を、大人になったいま観返すこと。そのなかで得た直観は、ここにありえたかもしれない現在の「父」の姿が予感されている、というものだった。いまだこの国に蔓延る家父長制の粉砕を夢見るとき、自身をフェミニストと自認しすこしでもマシな実践を模索するとき、「父」なるものの有害さばかりが意識され、「男らしさ」をそのまま悪なるものと断じてしまいたくなる。しかし現状を確認したときにすぐさま気がつくのは、打倒すべき「父」なるものはすでに失効しており、ただ構造としての家父長制だけが残置されているということである。産湯と共に赤子を流すというが、むしろ「よき父」という赤子だけが流されてしまい、居残った臭い産湯が「男」の本質であるかのように捉えられているのが現在の状況ではないだろうか。(…) では、「父」においてよきものとは何か。僕はこの問いを前に長年立ちすくんでいた。そのようなものが果たしてあるだろうか。「男」とは乱暴で汚らしいものでしかないではないか。内面化したミサンドリーに阻まれて、自身の性と向き合うことはなかなかに困難であった。そんななか、『ベイブ』を再発見したのである。当然、飛躍である。本稿は、映画論を方便としたごきげんな男性論の試みでもある。 (「はじめに」より)
-

ナショナリズムとセクシュアリティ 市民道徳とナチズム 文庫
¥1,760
SOLD OUT
何がリスペクタブルな振舞か。ナチズムへと至る国民主義の高揚の中で、性的領域も正常/異常に分けられていく。セクシュアリティ研究の先駆的著作。 === 18世紀の宗教復興とフランス革命を経て、西洋では「礼にかなった」作法を重んじる市民的価値観が浸透していった。リスペクタブルか否か? その問いかけはセクシュアリティをも正常/異常に区分し、国民主義と結びついて社会の管理・統制を強化した。逸脱行為と見なされた同性愛や売春は社会秩序を乱すものとされ、自制する「男らしさ」と、性欲を排した男同士の友情が市民道徳の基盤となっていく──。宗教、医学、芸術、性別分業、人種主義などの諸要素が絡まり合って作用し、市民的価値観と国民主義が手を取り合ってナチズムへ至る道が鮮やかに描き出される。文庫化にあたって、心理学者メアリー・ルイーズ・ロバーツによる新たな解説を付した。 === 「正常な性意識」が、ナチズムを支えた―― セクシュアリティ研究と歴史学を結んだ先駆的名著 === 目次 第1章 序論 国民主義と市民的価値観 第2章 男らしさと同性愛 第3章 身体の再発見 第4章 友情と国民主義(ナショナリズム) 第5章 どんな女性? 第6章 戦争と青年と美しさ 第7章 血と性――アウトサイダーの役割 第8章 ファシズムとセクシュアリティ 第9章 結論――万人の道徳 モッセ著作集版解説(メアリー・ルイーズ・ロバーツ) 一九九六年の訳者あとがき(佐藤八寿子) 訳者解題(佐藤八寿子) 原註 人名索引 著者プロフィール ジョージ・L・モッセ (ジョージ モッセ) (本文) ジョージ・L・モッセ(George L. Mosse):1918‐99年。ベルリン生まれ。ウィスコンシン大学・ヘブライ大学名誉教授。専門はドイツ社会史。1933年ナチスの迫害を逃れて亡命。37年ケンブリッジ大学入学。39年にアメリカ移住後、ハーヴァード大学で博士号を取得。著書に『大衆の国民化』『英霊』(ともにちくま学芸文庫)などがある。 佐藤 卓己 (サトウ タクミ) (翻訳) 佐藤卓己(さとう・たくみ):1960年生まれ。京都大学大学院教育学研究科教授。 佐藤 八寿子 (サトウ ヤスコ) (翻訳) 佐藤八寿子(さとう・やすこ):1959年生まれ。Kollegium Kyoto代表。
-

アイヌもやもや
¥1,760
SOLD OUT
【漫画『ゴールデンカムイ』の監修にも参加!北原モコットゥナシがアイヌをとりまくもやもやを丁寧に解説】 日本の民族的マイノリティであるアイヌ。北海道が舞台のドラマでもその姿を目にすることはめったになく、教科書に載っているのも民族衣装を着た姿ばかり。非アイヌにとって、今を生きるアイヌの姿は、まるで厚い「もや」の向こう側にあるかのようです。アイヌは、どんなことに「もやもや」を感じているのか? その「もやもや」はどこから来るのか? 無知・無理解や差別の構造、そしてマイノリティとマジョリティの関係など、北原モコットゥナシが様々な視点から考察してゆきます。 【アイヌが感じている「もやもや」を、田房永子が漫画で表現!】 母からの過干渉への葛藤や男性を中心に回る社会への疎外感を、鋭い視点でユーモアをもって描いてきた田房永子。本書では、アイヌが日常のなかで出会うさまざまな「もやもや」を田房氏の手によって漫画化しています。マジョリティに優位な社会の仕組みや、まわりからの無理解により、まるで虚を衝かれたような感覚に陥る瞬間など、漫画を通して感覚的に共有することができます。 <刊行に寄せて> 【北原モコットゥナシ 先生】 ※「シ」はアイヌ語小文字 「日本列島北部の先住民族」といわれるアイヌ。けれど、著者は東京都杉並区生まれのアイヌです。関東でも、北海道でも、アイヌのまわりには、いつも言葉にしにくいモヤモヤがついてまわり、視界を邪魔したり、息苦しくなったりすることも。モヤの正体を探っていくと、その向こうに、女性としてLGBTQ+として障がい者としてモヤを払う人々の姿がありました。そのお一人、田房永子 先生によって、けっして軽くはない、とらえにくいテーマを、魅力的で柔らかな絵柄とともにお伝えできることとなりました。 【田房永子 先生】 「アイヌもやもや」のお話をいただいた時は、「アイヌのことに完全に無知な私が携わっていいのだろうか」という不安がありました。 でも、北原モコットゥナシ先生の文章を読ませていただき、アイヌの人たちの視点を通して見る世界が、私が女性として生きてきた中で納得がいかなかったことと通じているところがあると知って、ぜひ漫画を描かせてもらいたいと思いました。 北原先生の文章はとても面白く分かりやすくて、無自覚だった自分のマジョリティの部分も刺激され、この社会の構造を、よりクリアに捉えることができるようになったと感じています。漫画では、東京で生まれ育ったアイヌの少年・颯太を主人公に、彼をとりまく人々を描きました。ぜひたくさんの人に読んでもらいたいです。 目次 Contents 第1章 言い出しにくいんです 第2章 差別・ステレオタイプ 第3章 アイデンティティ わたしらしさとアイヌらしさ 第4章 マジョリティの優位性 北原モコットゥナシ × 田房永子 特別対談 これまでのできごと年表 著者プロフィール 北原モコットゥナシ (キタハラモコットゥナシ) (著/文) 【北原モコットゥナシ】※「シ」はアイヌ語小文字 1976年東京都杉並区生まれ。北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授。アイヌ民族組織「関東ウタリ会」の結成に両親が関わったことで、文化復興や復権運動をはだで感じながら育つ。13歳のころ、北海道に暮らす祖母、小田トーニンテマハの影響でアイヌ語樺太方言や樺太アイヌの文化に関心をもつ。和名は北原次郎太。 田房 永子 (タブサ エイコ) (イラスト) 【田房永子】 1978年東京都千代田区生まれ。漫画家、エッセイスト。2001年、アックスマンガ新人賞佳作受賞。母からの過干渉に悩み、その確執と葛藤を描いたコミックエッセイ『母がしんどい』(KADOKAWA/中経出版)を2012年に発行。大きな反響を呼ぶ。他にも『キレる私をやめたい』(竹書房)、『上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください!』(上野千鶴子氏と共著、大和書房)など著書多数。
-

小学校就学サポートBOOK 障がいのある子と親のための
¥2,090
SOLD OUT
本書は、障害のある子どもが小学校に就学する時に、様々な困難を感じたり、就学先に悩んだりする親に寄り添うサポートBOOKです。 障害のある子どもが就学する時には、パートナーや行政、学校の先生など、様々な人と協力して、より良い学びの場を準備をする『就学活動』を行います。しかし、就学活動の道のりでは、慣習に沿った就学先を進められる、希望する学校に受け入れてもらえない、など思わぬトラブルに直面することがあります。この本は、そんなトラブルを事前に知り、先輩家族が実際に行った対応策を学ぶとともに、スケジュールに沿っていまやるべきToDoをひとつずつ行うことで着実に就学活動を前に進めていくことができる一冊となっています。 支援が必要な子も、そうではない子も、いつも隣にいて互いに心から笑い合える。それが当たり前で、誰もが生きやすい社会へ少しでも近づくはじめの一歩になることを願って、本書を発売いたします。 本書は、知っておきたい基本的な用語やスケジュールを学ぶ「PART1知識編」、お子さんが年中〜就学先決定までのToDoとトラブルを知り対応策を身につける「PART2実践編」、就学先決定〜入学までの小学校とのやりとりをまとめた「PART3準備編」で構成されています。また、コラムとして知っておきたい法律や障がいに対する考え方も満載。 小学校就学サポートBOOK 3つの特徴 1. 就学活動で直面するトラブルと対応策がわかる! 本書では、就学活動中に出会うかもしれないちょっと癖のある人を動物にたとえ、直面するトラブルをマンガ形式で紹介します。併せて、そのトラブルに対してこれまで就学活動を経験した先輩家族が実践した対応策=”こうしよう術”を掲載。事前にトラブルを知っておくことで、心構えと対応できる術を身につけることができます。 2. 当事者の実体験を元に年中〜年長の間のToDoがまるっとわかる! 就学活動ははじめてのことだらけ。それゆえ、これから何が起こるのか、何をすればいいのかわからないという悩みを抱える方が多いです。本書では、余裕を持って準備できる、お子さんが年中の時〜本格的に就学活動が始まる年長の時までにやるべきことをToDoとしてまとめています。それぞれのToDoでは、参考となる事例や知識を紹介します。 3. 学校を決めるための思考整理シートでお子さんに合う小学校がわかる! 就学活動で多くの方が悩むのは「自分の子どもにどの学校があっているかわからない」ということ。本書では、まず子どもの特性をや家族の考えを整理する「モヤモヤ整理シート」、学校見学時に学校の違いを比較できる「学校みくらべシート」など、学校を決めるための思考や情報の整理を助けるシートを収録。
-

[再入荷待ち]親切で世界を救えるか ぼんやり者のケア・カルチャー入門
¥2,090
SOLD OUT
なぜ鬼の頸(くび)が斬れない剣士・胡蝶しのぶは子どもたちの人気者になったのか? 『エモい古語辞典』『不道徳お母さん講座』『女の子は本当にピンクが好きなのか』の著者、注目の最新作。 『鬼滅の刃』から『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』『すずめの戸締まり』『ミッドサマー』『コンビニ人間』『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』――現代のポップカルチャーを支えるキーワードは、「ケア」。 流行りの「ケア」ってちょっと難しそう……? でも、私たち大人だって、人に優しく、思いやって生きていきたい。 「ケア」=抑圧的で退屈でつまらない 虚無と冷笑の時代を終わらせ、 「ケア」できる人=かっこいい! の時代へ。 ●愛される「学級委員的」キャラクター、竈門炭治郎と胡蝶しのぶ(アニメ『鬼滅の刃』)●「経済人」予備軍として扱われる大学生、責任主体とみなされない主婦(『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?』)●ヒロインは家父長制にとらわれた退屈なお母さん(映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』)●家父長制の国のハロウィン 暴動からボン・ジョヴィへ(統一教会との関連が取りざたされる「家庭教育支援条例」と岸政彦『断片的なものの社会学』)●コントロールできない人生とナラティブ・セラピー(アニメ『平家物語』)●親切≠道徳 絆ではなく親切で繫がるには(映画『すずめの戸締り』) ネットで話題の連載が待望の書籍化。 〈目次〉 はじめに 第1章 ケアの復権 『鬼滅の刃』にみるケアの倫理 /ケアの価値を見直す 胡蝶しのぶと『ビルド・ア・ガール』 /学校道徳と「家庭の天使」から遠くはなれて /「ケア」と「面白」は和解せよ 九〇年代的冷笑と現代の「ケアする」ツッコミ/学生運動の挫折と冷笑主義 母校の高校紛争体験記を読む 第2章 暗がりから見つめるケア 子どもの言葉を聞き続けるということ 映画『カモンカモン』の「暗がり」/「人間」を疎外するシステムで、包摂される人々/『コンビニ人間』『ウ・ヨン ウ弁護士は天才肌』/読む女、手を動かす女 「かけ足が波に乗りたるかもしれぬ」『ミシンと金魚』 アニメ版『平家物語』にみるケアとセラピー/ぼんやりプリンセスとケアするヒーローのときめきの魔法 映画『金の国 水の国』とこんまりメソッド 第3章 家父長制に抗うケア カルトは家庭の顔をする 『母親になって後悔してる』『ミッドサマー』/『教えて?ネコのココロ』から考える猫と家父長制 /家父長制の国のハロウィン 暴動からボン・ジョヴィへ /主婦バイトが『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?』を読んだら/絆ではなく「親切」でつながるには 第4章 ケアの復権 『エルピス』が描く、守るべき者がいる人間の弱さと悪について /親切で世界を救えるか 『すずめの戸締まり』『ローズウォーターさん、あなたに神のお恵みを』 /磔にされることなく「親切になろう」と言うために 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』 あとがきにかえて――こねこのぴっちが家出をした日 著者について 堀越英美(ほりこし・ひでみ) 1973年生まれ。文筆家。著書に『紫式部は今日も憂鬱 令和言葉で読む「紫式部日記」』(扶桑社)、『エモい古語辞典』(朝日出版社)、『女の子は本当にピンクが好きなのか』・『不道徳お母さん講座』・『モヤモヤする女の子のための読書案内』(河出書房新社)、『スゴ母列伝』(大和書房)、訳書に『自閉スペクトラム症の女の子が出会う世界』(河出書房新社)、『「女の痛み」はなぜ無視されるのか?』(晶文社)、『ギタンジャリ・ラオ STEMで未来は変えられる』(くもん出版)、『ガール・コード』(Pヴァイン)など。 Kindle→https://amzn.to/3NrGevT
-

このゆるい歯茎は私のせいじゃない
¥1,500
SOLD OUT
日記本、2023.11月刊行、B6、134p。 2023年1月21日から7月31日に書いた日記をまとめました。2022年の秋に仕事を辞めて、その直前に悪化させてしまったメンタルとさまざまな体調不良と共に暮らしています。 中学生の頃学校に行かなくなって毎日家にいたら、高校生になる頃にはその時期の記憶がすっぽり抜けてしまいました。また忘れるのは寂しいので日記を書き続けられているのかもしれません。どこかで密かに眠っているあなたのために、この日記を捧げます。 2023年10月20日 ほに 以下抜粋---------------------------------------------- ハロワに行かなきゃいけないが、なかなか準備ができない。何を食べたいのか分からなくて混乱する。声が出なくなる。おにぎりを与えられる。米かパンかすらも自分で決められないことがある。私は、私がどうしたいのか、私自身が命令を下す機能を失ってしまうことがある。それも頻繁に。 ・・・・ 眠れなかった朝カレー、寝落ち、気圧の急降下。同居人にいってらっしゃいを連呼して、ひとりねむる。気圧が横ばいになってようやく起き上がる。気圧が上がる、また眠る。 ・・・・ 300個以上開いていたスマホブラウザのタブが全部消えてしまって、自分が欠けたような気持ちになる。読みたかったインタビューのタイトルも本のタイトルも思い出せなくて、全部忘れろという体からのメッセージなのかも、と思う。 ・・・・ 本屋がなければ私なんてとうに死んでいた。教室の隅で、体ごと溶けてしまって。ゲロを吐くように文章を吐き出す事で鎮められる感情があるなら、あなたのようにお茶目で不器用な男の子になりたかった。
-

ころがるいきもの
¥1,500
SOLD OUT
友達のほにと暮らしています。 日記屋月日のワークショップに参加して書いた2023年2月〜4月の日記と、数日間の記録です。 生活が上手くなく、床に転がりながらも生き延びていた頃の日々を綴っています。マッチングアプリで友達をつくったり、ピクニックをしたり、ウィメンズマーチや選挙に行ったりしています。 抜粋 _______________________ 2月11日(土) 珍しく友達が先に起き上がる朝。お腹が空きすぎてとっくに目は覚めていたけれど、3時間くらいそのまま布団の上にいたらしい。二人ともチョコ系のパンを食べて、足りなくて追加でスープを飲んで、日暮里へ。わたしはブラウスに合わせるつけ襟を作りたくてレースを、友達は還暦を迎えたお母さんに贈るぬいぐるみ用の布を繊維街で買う。他にも直感的に良いなと思えたものや、なんとなく役立つだろうと思ったものも買った。夢中になって店を回ってたらいい時間になり、展示へ向かう。『クィアな地平線』というタイトルのグループ展。キュンチョメの映像作品『声枯れるまで』は、トランスジェンダーやクィア当事者へ名前を変えた経緯を聞き、自分で新しくつけた名前を一緒に声枯れるまで叫ぶというものだった。私は下の名前に〝 子 〟が付くのがなんだか少し古臭く、女の子に付ける名前という感じがしてあまり気に入っていない。中学の時、クラスの女の子が「名前に〝 子 〟が入るのダサくない?」とこちらに聞こえる声量で言っていた記憶が蘇る。その子に最近子供が産まれた。名前に〝 子〟は入ってなかった。
-

ニュ(ー)シティサンヒルズ
¥1,000
SOLD OUT
恋愛わからんマンの13番館が暮らすアパート、ニュ(ー)シティサンヒルズ。二人はノリで始めたマッチングアプリのプロフィール欄に、自己紹介の代わりに日記を書くようになった。 自分と似た感覚を探すために、誰かの理想に抵抗するために、あるいは誰かへの私信として。交差する生活の記録。 2020年、2021年のそれぞれ1か月ほどの日記を収録しました。 2022年12月11日初版発行 制作:13番館 デザイン:ひろの 判型:A5 ページ数:40ページ 価格:税込1,000円