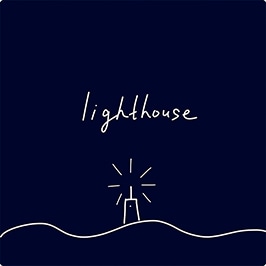こちらのウェブストアは運営停止しています。
購入は新ストア(以下のボタンをクリック)よりお願いします。
*Tシャツなどのグッズはこちらで購入可能です。
-

おぺん選書便(3冊/5500円くらいのやつ)
¥5,500
SOLD OUT
本3冊+lighthouseロゴトートバッグ1つのセットです。 本3冊でだいたい5500円(税込)くらいになるように選書します。 設定金額に届かない分をトートバッグで吸収するスタイルです(トートバッグ単体は1000円+税で販売中)。 備考欄に ・トートバッグの色(ナチュラル/ネイビー) ・読みたいジャンルやテーマ(3つまで) ・くわえてNGのジャンルやテーマ、作家などがあれば(これは読みたくない!というものを知れたほうがありがいもので……) ・そのほか細かい希望があれば遠慮なくどうぞ あたりをご記入ください。 この本は入れてくれ、という「注文」もなんなりと。 そのほか質問などあればお問い合わせくださいませ。 *1万円選書のサービス「ブックカルテ」にも参加していますので、そちらのご利用も大歓迎です https://bookkarte.com

-

ユリイカ2024年1月号 特集=panpanya
¥1,760
SOLD OUT
商業誌デビュー10年・単行本10冊目刊行記念 「端切れ」を拾い、観察し、想像するというプロセスからpanpanyaのマンガは生成される。「寝入りばなにみる夢のよう」とも形容され、時に「ガロ系」をはじめとする日本のオルタナティヴ・コミックの水脈上に位置づけられるその仕事は、まるで終わらない自由研究のように拡大と深化を続けている。最新刊『商店街のあゆみ』の刊行に際し、拾い集められてきた「端切れ」たちを改めて見つめ直し、それらによって形成された架空の町の中でこれからも道に迷い続けるための地図を想像したい。 目次 特集*panpanya──夢遊するマンガの10年 ❖マンガ 予告 / panpanya ❖インタビュー 名残を描く / panpanya 聞き手=可児洋介 ❖渚にて 「街」と「私」──日本におけるオルタナティヴ・コミックの水脈 / 可児洋介 波よ、楽園まで届け──『楽園Le Paradis』という媒体=場をめぐって / 雑賀忠宏 ❖かたちを作る 心に残るもの / 飯田 孝 ユカイが集う あの場所へ──SF研究会とコミティアと / 吉田雄平 正体 / 多治見武昭 資料性みやげ / 國澤博司 ❖伝播するできごと 索引と屁理屈、そしてpanpanya 的小事件 / 春日武彦 panpanyaの主題による四つの変奏 / 細馬宏通 ❖再録 後輩ちゃん / panpanya ❖trans/duce 彷徨の体 / 酉島伝法 動物、世界の内側 / おいし水 ❖描線の夢・紙の現(うつつ) panpanyaのマンガ作品における非・キャラクター / 森田直子 寝入りばなの夢のつづきかた / 中田健太郎 環境の共同 / 木下知威 ❖往復書簡 地図の研究 / panpanya×青柳菜摘 ❖イラスト・マンガギャラリー〈1〉 ある日のpanpanyaさん / 竹本 泉 群棲地の置き場所 / 平方イコルスン panpanya作品との出会い / kashmir 時間と濃淡 / 犬のかがやき ❖彷徨と変異 逸脱者たちが見る不思議の国の夢 / トジラカーン・マシマ A Little Girl Lost / 石井美保 ❖compound angle レオナルドとの会話、あるいは現実と非現実の硲(はざま)について / 渕野 昌 panpanyaさんについて / 八谷和彦 ❖モノへの眼差し 「架空の通学路について」についての架空の考現学講義──あるいは〈考現学マンガ〉研究序説 / イトウユウ 少女たちの眼と不可思議 / 寺村摩耶子 自律した(リアルな)モノとモノとが創るモノがたり(フィクション) / 本橋 仁 ❖イラスト・マンガギャラリー〈2〉 彷徨 / カシワイ 風景 / 飯島健太朗 パンパンヤさんありがとうございました / 西村ツチカ 卵をめぐる漫画の探索 / 速水螺旋人 ❖ジオラマの肌理 本物の街 / 石山蓮華 スクールゾーンの空想科学 / 木石 岳 歌ってない歌 / 斎藤見咲子 ❖揺らぎを見つめる 真面目な異界めぐり──panpanyaのマンガ作品における行動原理についての覚書 / 川崎公平 転がるおむすび、兎の穴へ降る──観察・日常の謎・陰謀論 / 荒岸来穂 ❖資料 panpanya全単行本解題 坂本 茜 ❖忘れられぬ人々*27 故旧哀傷・菅野昭正 / 中村 稔 ❖物語を食べる*35 妖精と出会うこと、病むこと / 赤坂憲雄 ❖詩 夕焼け、または、わが魂の行衛 他三篇 / 中村 稔 ❖ユリイカの新人 三面鏡 / 山内優花 パミス 他一篇 / のもとしゅうへい ❖われ発見せり 老学徒と『鉄拳』の出逢い / 平井和佳奈 表紙・扉イラスト……panpanya 目次・扉……北岡誠吾 Kindle→https://amzn.to/3vc1cZj
-

彼女たちのまなざし 日本映画の女性作家
¥2,640
SOLD OUT
女性映画作家たちのまなざしからよみとく日本映画の最前線。 “「映画監督」と呼ばれる人々が一人残らず女性であったなら、当然そこに「女性監督」という呼称は生まれえない。かつて映画監督には、男性しかいないとされていた時代があった。”(「序論」より) そのような時代は果たして本当の意味で「過去」となりえているのだろうか? 本書は、この問題提起を出発点として、日本映画における女性作家の功績を正当に取り上げ、歴史的な視座を交えながらその系譜をたどり、彼女たちのまなざしから日本映画の過去・現在・未来を読み替えていくことを試みる、これまでにない映画批評である。 対象をあえて女性のみに限定し、大勢の男性作家たちのなかにいる数少ない女性作家という図式をまずはいったん解体することから始めるというアプローチから、これまでの日本映画の歴史にひそむ性の不平等や権力の不均衡の問題にせまり、日本映画史の捉え直しを通して、新しい地図を描き出す。 伝統的な家父長制から脱却し、多様な属性とオルタナティヴな関係性を個々人が模索する2020年代以降の時代精神から読みとく、日本映画の最前線。 取り上げる主な作家 西川美和、荻上直子、タナダユキ、河瀨直美、三島有紀子、山田尚子、瀬田なつき、蜷川実花、山戸結希、中川奈月、大九明子、小森はるか、清原惟、風間志織、浜野佐知、田中絹代……ほか多数 論考から作品ガイドまで、全原稿書き下ろし 作家ごとの評論だけでなく、日本映画史における女性監督の系譜、次世代の新進作家紹介、今見るべき日本の女性監督作品の100本ガイドまで。作家論、歴史、状況論、作品ガイドまでを網羅した、著者渾身の書き下ろし。 === ◎目次 序論 児玉美月 第1章 日本映画における女性監督の歴史 北村匡平 1 女性監督のパイオニア/2 胎動期──1950〜1980年代/3 黎明期──1990年代/4 ニューウェーヴ──2000年代/5 黄金期──2010年代以降 第2章 16人の作家が照らす映画の現在地 北村匡平+児玉美月 1 西川美和論──虚実、あるいは人間の多面性 2 荻上直子論──「癒し系」に「波紋」を起こすまで 3 タナダユキ論──重力に抗う軽やかさ 4 河瀨直美論──喪失と再生を描く私映画 5 三島有紀子論──陰翳の閉塞空間とスクリーン 6 山田尚子論──彼女たちの空気感と日常性 7 瀬田なつき論──どこにもない「時間」を生きる 8 蜷川実花論──恋と革命に捧げられた虚構の色彩 9 山戸結希論──すべての「女の子」たちへ 10 中川奈月論──世界の崩壊/解放と階段のサスペンス 11 大九明子論──意外と「だいじょうぶ」な女たち 12 小森はるか論──記録運動としての積層と霊媒 13 清原惟論──マルチバースで交感する女性身体 14 風間志織論──日常の細部を照らし出すフィルム 15 浜野佐知論──男根的要請とフェミニズム的欲望の闘争 16 田中絹代論──欲望する身体とセクシュアリティ 第3章 次世代の作家たち 児玉美月 「映画」が孕む暴力性への自覚/日本の社会問題と向き合う/独自の作家性を貫く/学園映画の異性愛規範に抗する/オルタナティヴな関係性を模索する/新たな属性を可視化させる/まだ見ぬ未来へのシスターフッド 〈付録〉女性映画作家作品ガイド100 児玉美月+北村匡平 あとがき 北村匡平 著者について 北村匡平(きたむら・きょうへい) 映画研究者/批評家。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授。単著に『椎名林檎論——乱調の音楽』(文藝春秋、2022年)、『アクター・ジェンダー・イメージズ——転覆の身振り』(青土社、2021年)、『24フレームの映画学——映像表現を解体する』(晃洋書房、2021年)、『美と破壊の女優 京マチ子』(筑摩書房、2019年)、『スター女優の文化社会学——戦後日本が欲望した聖女と魔女』(作品社、2017年)、共編著に『川島雄三は二度生まれる』(水声社、2018年)、『リメイク映画の創造力』(水声社、2017年)、翻訳書にポール・アンドラ『黒澤明の羅生門——フィルムに籠めた告白と鎮魂』(新潮社、2019年)などがある。 児玉美月(こだま・みづき) 映画文筆家。共著に『反=恋愛映画論——『花束みたいな恋をした』からホン・サンスまで』(ele-king books、2022年)、『「百合映画」完全ガイド』(星海社新書、2020年)、分担執筆に『ロウ・イエ 作家主義』(A PEOPLE、2023年)、『デヴィッド・クローネンバーグ 進化と倒錯のメタフィジックス』(ele-king books、2023年)、『フィルムメーカーズ24 ホン・サンス』(宮帯出版社、2023年)、『ジャン=リュック・ゴダールの革命』(ele-king books、2023年)、『韓国女性映画 わたしたちの物語』(河出書房新社、2022年)、『アニエス・ヴァルダ——愛と記憶のシネアスト (ドキュメンタリー叢書)』(neoneo編集室、2021年)、『岩井俊二 『Love Letter』から『ラストレター』、そして『チィファの手紙』へ』(河出書房新社、2020年)、『フィルムメーカーズ21 ジャン=リュック・ゴダール』(宮帯出版社、2020年)など多数。『朝日新聞』、『キネマ旬報』、『文藝』、『ユリイカ』、『文學界』などに寄稿。
-

IMONを創る
¥1,980
SOLD OUT
◆◆◆『ぼのぼの』、『I【アイ】』、『誰でもないところからの眺め』のいがらしみきおによる、幻の予言的文明論にして不朽の人間哲学、30年の時を経て復刊!◆◆◆ 80年代末から90年代初頭にかけて雑誌『EYE・COM』(アスキー)で連載され、1992年に書籍化されたいがらしみきおの長篇エッセイ『IMONを創る』。 「人間のためのOS(オペレーティング・システム)」である「IMON」=「いつでも・もっと・おもしろく・ないとなァ」の構築を目指して書かれた本書は、著者の作品群を貫く思想と人間観が凝縮された一冊でした。 その刊行から30年後の現在、一人一台スマートフォンを持っているのが当たり前のSNS社会の風景は、『IMONを創る』で予言されていた世界像そのもの。 驚くべきはその予見の精確さだけではなく、そこで提唱された「IMON」というOSのアイデアが、AI産業の隆盛により人間というものが急速に相対化されつつある現代において、それでも人間が人間として、いつでも・もっと・おもしろく生きていくために、より刺激的かつ有効なものとなっていることです。 前世紀最大の奇書であり、精確な思考が現実の未来を射抜いた驚異の予言書であり、人間世界の「ぜんぶの解説」とも言うべき本書を、著者自身の新しいあとがきと、本書の熱読者である作家・乗代雄介氏による解説を付し、復刊します。 目次 まえがきマンガ 5 第1部 IMON創世記 TRONより早く実現するかもしれないユーザー側のOSを考案 8 5年のキャリアをもつ、IMONプロジェクトの人工無脳とは? 14 コンピューターは生き物か? アイデンティティーを与える 19 アメリカのコンピューター事情(?)を探ってきた成果は? 24 TRON住宅より早く完成した“IMON住宅”。その住み心地は? 30 矛盾がでてきてしまったIMONの“生き物理論”。その結果は? 35 コンピューターの新呼称キャンペーンを大展開。IMON第一部完 40 第2部 オタクから超常現象へ テーマ形式に変更した第2部。今回はオタクについて 46 メディアのディスプレー化で誕生したオタク層。断絶した世界を行く 51 ニッポン全国総オタク時代。オタクを笑うもの、オタクに泣く! 56 “オタク”、このテーマも今回が最後。問題点を総括した結論とは? 61 理論は不確定なものである。“超常現象”により覆される二値理論!? 67 ビッブにおいても超常現象はあるか? 実験を行なうIMON 72 ビッブに超常現象はないとするIMON。新たな事実が生まれるか? 77 『ふたりのビッブナイト』譜面 82 第3部 IMON3原則に迫る “いつでももっとおもしろくないとな”がモットー。第3部の開始だ 84 アナタは円周率を何ケタまで覚えてますか? 今回は数学的に迫る 90 聖書のように、マカズ、カラズ、クラニオサメズには生きていけない 96 プログラム言語Idaによって明らかにされる“マルチタスク” 102 IdaによってかかれたふたつのOS、I-IMONとG-IMON 108 儀礼と定型をつかさどるだけではないOS、G-IMONとはなにか? 114 一般の人にとってのG-IMON、表現とはなんだろうか? 120 今回は方程式を使って解説をするIMONの3原則“(笑)”の項 126 IMONの3原則“(笑)”を科学的に現象学で立証してみる 132 IMONの3原則“(笑)”最終回。『IMONを創る』第3部終了 138 IMON認定ソフト第1弾『トーキングぼのぼの』 144 第4部 IMONとパソコン通信 人間としてのアイデンティティーを消去させられるパソコン通信とは 146 パソ通は、アイデンティティーを剥奪されたものの上に成立する!! 152 パソコン通信について語るのも、これが最後なのだ!! 158 ハードについて考える。第1回を振り返ってみてほしい 164 ソフトウェアが進む“便利へ”と“快楽へ”のベクトル 170 IMON認定ソフト第2弾『BBSちゃん』 176 第5部 ビッブの教育と未来 IMON、最終章の(?)第5部に突入だ! 178 ビッブが言葉に意味を与えたとき、もうひとりの自分が出現する! 184 ビッブを教育するという立場から、人は決して逃れえないのだ 190 “宗教なしで人間的生活を営むことは可能か否か”を解き明かす! 196 IMONのリアルタイムやマルチタスクを実現できる唯一の国 202 『IMONを創る』は終わるが、IMONの歴史はこれから始まる! 208 その後のIMON 214 「その後のIMON」のあと 216 解説 私と『IMONを創る』の二十年 乗代雄介 222 著者プロフィール いがらしみきお (イガラシ ミキオ) (著/文) 1955年宮城県中新田町(加美町)に生まれる。24歳で漫画家デビュー。代表作に「あんたが悪いっ」(1983年漫画家協会賞優秀賞)、「ぼのぼの」(1988年講談社漫画賞)、「忍ペンまん丸」(1998年小学館漫画賞)、「I(アイ)」、「羊の木」(2015年文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞)、「誰でもないところからの眺め」(2016年漫画家協会賞優秀賞)など。現在「ぼのぼの」がフジテレビ系列でアニメ放映中。仙台市在住。
-

『ベイブ』論、あるいは「父」についての序論
¥1,200
SOLD OUT
著:柿内正午 幼少期に自身を魅了した映画を、大人になったいま観返すこと。そのなかで得た直観は、ここにありえたかもしれない現在の「父」の姿が予感されている、というものだった。いまだこの国に蔓延る家父長制の粉砕を夢見るとき、自身をフェミニストと自認しすこしでもマシな実践を模索するとき、「父」なるものの有害さばかりが意識され、「男らしさ」をそのまま悪なるものと断じてしまいたくなる。しかし現状を確認したときにすぐさま気がつくのは、打倒すべき「父」なるものはすでに失効しており、ただ構造としての家父長制だけが残置されているということである。産湯と共に赤子を流すというが、むしろ「よき父」という赤子だけが流されてしまい、居残った臭い産湯が「男」の本質であるかのように捉えられているのが現在の状況ではないだろうか。(…) では、「父」においてよきものとは何か。僕はこの問いを前に長年立ちすくんでいた。そのようなものが果たしてあるだろうか。「男」とは乱暴で汚らしいものでしかないではないか。内面化したミサンドリーに阻まれて、自身の性と向き合うことはなかなかに困難であった。そんななか、『ベイブ』を再発見したのである。当然、飛躍である。本稿は、映画論を方便としたごきげんな男性論の試みでもある。 (「はじめに」より)
-

正義はどこへ行くのか 映画・アニメで読み解く「ヒーロー」
¥1,056
SOLD OUT
「多様性」の時代のヒーローとは── 【推薦コメント】 本書はヒーローの変遷を歴史的な流れのなかで見通すひとつの示し、手がかりを与えてくれる。 ────三木那由他氏(大阪大学大学院講師・『言葉の風景、哲学のレンズ』、『会話を哲学する』) 【おもな内容】 世界を救う、「正義」の象徴たるヒーローは、圧倒的な“マジョリティ”として表象されてきた。 しかし21世紀を迎え、ジェンダー、加齢、障害、新自由主義といった様々な観点への理解・変化から、留保なしでその存在は認められなくなった。 では、ヒーローたちはどのように「多様性」と向き合うのか? そして、「ポスト真実の時代」とどう対峙していくのか? 本書は、ヒーローの誕生から発展までの歴史的視座を参照し、アメリカと日本のポップカルチャーに登場、活躍する《新しいヒーロー像》を縦横無尽に論じる。 ヒーローを考えることは社会を考えることだ! 【目次】 序章 多様性の時代の正義 第一章 法の外のヒーローたち 第二章 二つのアメリカと現代のテーレマコス 第三章 トランプ時代の「お隣のヒーロー」 第四章 多様性の時代に「悪」はどこにいるのか? 第五章 「オレはまだまだやれる!」──中年ヒーローの分かれ道 第六章 障害、加齢とスーパーヒーロー 第七章 日本のヒーローの昔と今 第八章 正義のパロディとニヒリズムとの戦い 第九章 デスゲームと「市場」という正義、そしてケアの倫理へ 第十章 ポストフェミニズムと新たな「ヒーロー」 終章 私たちの現在地 おわりに 正義はどこへ行くのか? 【著者略歴】 河野真太郎(こうの・しんたろう) 1974年、山口県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学。 博士(学術)。 専修大学国際コミュニケーション学部教授。 専門はイギリス文学・文化およびカルチュラル・スタディーズ。 著書に『はたらく物語 マンガ・アニメ・映画から「仕事」を考える8章』(笠間書院)、『新しい声を聞くぼくたち』(講談社)、『増補 戦う姫、働く少女』(ちくま文庫)、翻訳にウェンディ・ブラウン著『新自由主義の廃墟で』(人文書院)など多数がある。 Kindle→https://amzn.to/3GFGa87
-

別冊のん記 妻のレコードおつかい編
¥550
SOLD OUT
新書サイズ/56p/本文モノクロ/ 2022年11月20日発売 初版 「この盤をサルヴェージしていたことに驚きを隠せませんでした。」 矢野利裕(批評家、DJ) イラストレーター、漫画家、歌人のスズキロクによるエッセイ4コマシリーズの新作です。 DJでもあり、常にレコードを集める趣味の「夫」と、レコードのことはさっぱりわからない「妻」。 夫のヒントを便りに、妻が予算1万円での「レコードおつかい」にチャレンジ! 妻は見事に正解にたどり着けるか!? 実際に妻が購入したレコードの解説付きです。(解説は矢野利裕執筆)
-

別冊のん記 妻のレコードおつかい編 リターンズ
¥1,100
SOLD OUT
新書サイズ/114p/本文モノクロ/ 2023年11月11日発売 初版 あの「レコードおつかい」がパワーアップして帰ってきた! レコードにまったく詳しくない妻が、 レコードに詳しい友人たちのヒントだけを頼りにおつかいチャレンジ! 今回も予算は(夫の)1万円! はたして妻は今度は何のレコード買ってきたのか!? エッセイ4コマシリーズ『よりぬきのん記』のスピンオフ企画第3弾。 (ここから読んでも大丈夫!前作を読むとさらに面白い!) お題提供・レコード解説に豪華ゲストをお迎えした新作。 ネオアコ編のゲストはTBSラジオプロデューサーの長谷川裕さん、 ジャズ編のゲストは音楽評論家の柳樂光隆さん! おつかい代提供&監修は今回も夫・矢野利裕! スズキロクによる、おつかいレコードジャケットを再現したイラストもお楽しみください。
-
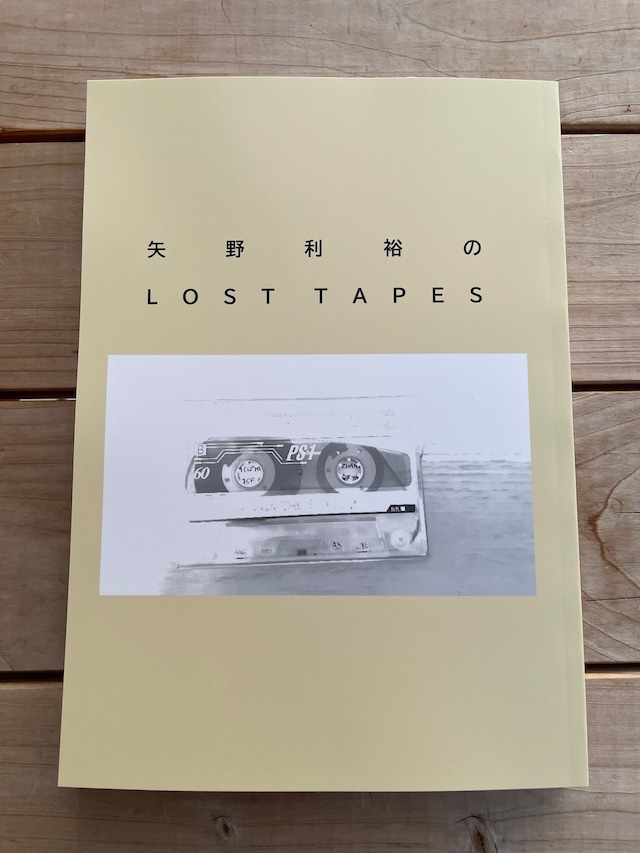
矢野利裕のLOST TAPES
¥1,650
SOLD OUT
矢野利裕がブログ・note・雑誌などで執筆した単行本未収録原稿をまとめた「矢野利裕のLOST TAPES」
-

すきのあいうえお
¥2,200
SOLD OUT
「美しいより、おもしろく。意味があるより、おもしろく」。 こんなキャッチフレーズで全国を巡回中の「谷川俊太郎 絵本★百貨展」のために、詩人の谷川俊太郎と写真家の田附勝が絵本を作った。本のテーマは「すき」。谷川がすきなもの、すきな言葉を、「あ」から「ん」まで順にあげていき、田附が日本全国を旅して写真を撮った。 「すき」は、谷川俊太郎がすきな言葉の一つ。本や詩集のタイトルにもたびたび登場する。「すき」は、誰もが自由に思い、表明することのできる、明るく肯定的な感情だ。「あ」から「ん」までの、谷川と田附が表すさまざまな「すき」を見ていると、生きるパワーと、未来への希望が体を満たす。 「すきのあいうえお」をみんながやったらいいね、と谷川はいう。自分の「すき」を言葉にしてみると、ああそうか、と、忘れていた自分を発見する。そして嬉しくなって、自分のことがすきになる。『すきのあいうえお』はそんなことを提案する、おもしろい本だ。 著者プロフィール 谷川俊太郎 (タニカワシュンタロウ) (文) 1931年生まれ。詩集『二十億光年の孤独』、絵本『ことばあそびうた』、訳書『マザー・グースのうた』ほか著書多数。希望の眼差しをもって、言葉を中心とする表現に挑み続ける詩人。 田附勝 (タツキマサル) (写真) 1947年生まれ。2012年に『東北』で第37回木村伊兵衛写真賞を受賞。社会で見過ごされてしまうものに突き動かされ、写真のテーマとして撮影を続けている写真家。
-

頭のうえを何かが Ones Passed Over Head
¥2,530
SOLD OUT
「ストローク(脳梗塞)は僕にとって恩寵でした。そして深い教えでした。」 『抽象の力』(第69回芸術選奨文部科学大臣賞)の岡﨑乾二郎さんは、2021年10月に脳梗塞で倒れました。 倒れてから1ヵ月後に麻痺した右手で描いた40作以上の絵と「リハビリ記」(2万7千字)が収録されています。 本書は、カラー部分だけでも約100頁ある画集であり、病をも創造の糧とする示唆に溢れた手記でもあります。 【本書より】 2021年10月30日土曜日の23時でした。知り合いにPCでメッセージを送りはじめたときに指がもつれはじめ、腕から力が抜け、右手も右足も瞬く間に動かなくなりました。椅子からずり落ちるように、なんとか床に横たわりました。脳梗塞だと思いました。(リハビリ記 冒頭) 絵を再び描くなんてことはありえないと思い込んでいた一人の脳梗塞片麻痺患者にとって、目の前で出来上がっていく絵は、自分で描いたものであるにもかかわらず、人ごとのように驚きをもって見えたものである。だからスマホで家族やスタッフにそれを送った。ネコが自分が獲ったエモノ、見つけた事物を家人の手元に持っていって自慢するようなものである。(あとがきより抜粋) 著者プロフィール 岡﨑乾二郎 (オカザキケンジロウ) (著/文) 1955年東京生まれ。造形作家。批評家。セゾン現代美術館、豊田市美術館で大規模な個展を開催するとともに、美術批評を中心として執筆を続ける。主著に『ルネサンス 経験の条件』(文春学藝ライブラリー)、『抽象の力 近代芸術の解析』(亜紀書房/第69回芸術選奨文部科学大臣賞)、『感覚のエデン』(亜紀書房/第76回毎日出版文化賞〈文学・芸術部門〉)、『絵画の素 TOPICA PICTUS』(岩波書店)など。
-

透明人間 Invisible Mom
¥2,640
SOLD OUT
“見えないもの”とされているすべての母親たちへ—— 重い障害を持つ「医療的ケア児」にずっと付き添う母親が、校内で“わたし”自身にカメラを向けたとき、社会の問題が浮き上がってきた。 息子が重度の障害とともに生まれた日から、「私」は「医療的ケア児の母親」となった。特別支援学校へ入学すると、週のほとんどを校内で待機する日々。 「気配を消してください」と求められた私は、「私はここにいる」と言わんばかり、自分自身を写真に撮り始める。そこに写し出されたのは、「誰かのために生きる今」をそれでも楽しく生きようとする、私の姿だった――。 テーマとは不釣り合いに、つい笑ってしまう、明るくユーモアのある写真の数々。全国各地で開催される写真展にも共感の声が相次ぎ、メディア取材も多数。 「母親」「お母さん」として“透明になって”生きている一人ひとりに、エールをおくるような一冊。 2021年に著者が自費出版した『透明人間 Invisible mom』が大きな反響を呼び、ここに山崎ナオコーラ、櫛野展正の両氏の寄稿を加え、再構成・再編集して出版。 学校も病院も社会だ。付き添いもケアも家事も、社会活動だ。 お母さんは、社会人だ。社会を変えられる。――山崎ナオコーラ 表舞台には出てこない、「透明にされた」母親たちの思いを伝える 手段こそが、山本さんの写真であり言葉なのだろう。――櫛野展正 山本美里(やまもと・みさと) 1980年東京都生まれ。写真家、医療的ケア児の母。2008年、妊娠中に先天性サイトメガロウイルス感染症に罹患した第3子が障害を持って生まれ、「医療的ケア」を必要とする子の親となる。その息子が特別支援学校小学部に入学するとともに、週4日の校内待機の日々が始まる。2017年に京都芸術大学通信教育部美術科写真コースへと進み、息子に常に付き添う自分自身を被写体にした写真作品の制作を開始。同学学長賞も受賞した一連の作品を2021年11月に『透明人間 Invisible mom』として自費出版すると、大きな反響を呼ぶ。全国各地を展示と講演で回るさなか、2023年1月に櫛野展正氏による記事「隠された母親たち」がウェブ版「美術手帖」に掲載。それをきっかけに、『透明人間 Invisible mom』を再構成・再編集した本書を出版。同年、別作品で「MONSTER Exhibition 2023」優秀賞受賞。現在も医療的ケア児と特別支援学校の保護者付き添いをテーマに作品制作を続けている。 Website: https://inbisiblemom.studio.site/1 Instagram: @m.yama_moto
-

グラフィック・ビートルズ
¥3,960
SOLD OUT
ビートルズのアルバム11 枚のジャケット・デザインを1 章ずつ解説。デザインの「革新性」を20 世紀デザイン史の中に位置付け、「デザインの歴史探偵」を名乗るデザイナーの松田行正が検証します。 表紙に付けられたA1 判大のパロジャケ・コレクション・ポスター(CD180 点以上、書籍34 冊を掲載)も圧巻。書籍でしか味わえない造本の魅力が満載です。 目次 1 斜めがもたらした躍動感が新しい息吹を伝える。 Please Please Me 2 カメラマン、フリーマンの活躍❶ ハーフ・シャドーがビートルズのアイコンとなる。 With the Beatles 3 カメラマン、フリーマンの活躍❷ 映画のコマ撮り風デザインがサントラをイメージさせる。 A Hard Day’ s Night 4 カメラマン、フリーマンの活躍❸ タイトル・バンド名よりもヴィジュアルを重視する。 Beatles for Sale 5 カメラマン、フリーマンの活躍❹ 手旗信号風やらせポーズでアイドル路線に回帰する。 Help! 6 カメラマン、フリーマンの活躍❺ サイケデリック・フォントと憂鬱な表情が60 年代を象徴する。 Rubber Soul 7 髪の毛にこだわったイラストとコラージュで伝説となる。 Revolver 8 原寸コラージュによる集合写真。 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 9 経年変化をデザインする。 The Beatles(White Album) 10 なにげない日常の風景をアート、そしてアイコンにしてしまった。 Abbey Road 11 ビートルズの最後を象徴するかのように4 人を分断するレイアウト。 Let It Be この他にコラムが多数入ります。 著者プロフィール 松田 行正 (マツダ ユキマサ) (著) 本のデザインを中心としたグラフィック・デザイナー。自称デザインの歴史探偵。「オブジェとしての本」を掲げるミニ出版社、牛若丸主宰。『眼の冒険』(紀伊國屋書店)で第37 回講談社出版文化賞ブックデザイン賞受賞。著書に、『デザインってなんだろ?』(紀伊國屋書店)、『デザインの作法』(平凡社)、『にほん的』(河出書房新社)、『独裁者のデザイン』(河出文庫)、『眼の冒険』『線の冒険』(ちくま文庫)、『RED』『HATE !』『急がば廻れ』『デザイン偉人伝』『アート& デザイン表現史』『戦争とデザイン』『宗教とデザイン』(左右社)などがある。
-

夢と生きる バンドマンの社会学
¥2,860
SOLD OUT
人生を賭ける夢に出会えたことの幸福と困難――。いつの時代にも少数派ながら「卒業したら就職する」という、普通とされる生き方を選ばない者がいる。夢は諦めに終わるのか、形を変えて続くのか? 数年にわたる二十代から三十代のバンドマンへの貴重なインタビュー調査をもとに現代の「夢追い」のリアルな実態を描き出す。 目次 はじめに Ⅰ 「夢追いの社会学」の試み 序 章 夢追いの社会学に向けて 1 夢追い研究の到達点と課題 2 夢追いを「若者文化と進路形成」の問題として捉える 3 分析枠組み――「若者文化と進路形成」に向けて 4 調査の概要 第1章 夢追いの戦後史――若者はいかなる将来の夢を抱いてきたのか 1 将来の夢を跡づける 2 複数のデータをつなぎ合わせる・重ね合わせる 3 将来の夢の変化の全体像――JGSS-2006による分析 4 夢追い志向か、それとも安定志向か? 5 将来の夢のゆくえ――現代の夢追いの特徴とは何か Ⅱ 夢を追い始める 第2章 来歴と条件――夢追いの選択に踏み切る 1 夢追いの幕開け――〈教育〉と〈若者文化〉の関係から 2 音楽活動を始める 3 音楽活動を中心とした進路形成 4 夢追いの選択に踏み切る条件 5 〈教育〉から〈若者文化〉へ――「適応―離脱モデル」の視点 第3章 フリーターか正社員か――夢追いに伴う働き方の選択 1 フリーターとして夢を追い始める 2 なぜフリーターを選択するのか 3 なぜフリーターであり続けられるのか 4 そもそもフリーターになるべきなのか――正社員バンドマンの存在 5 夢を追うためにフリーターになるか、正社員になるか Ⅲ 夢を追い続ける 第4章 夢の中身と語り方――夢を変えて追い続ける 1 バンドマンはいかなる夢を追うのか 2 夢の中身が変わる 3 夢の語り方も変わる 4 夢の変化の背景 5 夢を変えるからこそ夢が追い続けられる 第5章 夢の調整と破綻――集団で夢を追う方法 1 バンドマンとしての夢追い、バンドとしての夢追い 2 バンドZの来歴 3 互いの夢を共有する 4 解散とその後――共有された夢の破綻、そして別々の人生へ 5 集団で夢を追い続けることのリアリティ――「音楽性の違い」とは? 第6章 批判と抵抗――ライブハウス共同体の機制と陥穽 1 批判されても夢を追い続ける 2 標準的ライフコースとの攻防 3 夢追いは反動的に維持される 4 ライブハウス共同体という準拠集団 5 ライブハウス共同体の生成・波及・限界 6 夢追いはどこまで続くのか Ⅳ 夢を諦める 第7章 挫折か納得か――夢を諦める二つの契機 1 「仲間がどんどんいなくなる」 2 第一の契機――身体的・精神的問題を抱えて 3 第二の契機――無視できなくなる将来への不安 4 だれのせい?――「やりたいこと」と自己責任の共振 5 夢追いの先へ――標準的ライフコースの呪縛 第8章 夢追いバンドマンのライフヒストリー――選択・維持・断念のつながり 1 夢追いライフコースをトータルに描く 2 分析の焦点 3 夢追いの選択から維持へ 4 そして夢を諦める 5 夢追いの幕引き 終 章 夢追いからみる現代社会 1 本書の知見 2 夢と生きる軌道――四領域モデルからの考察 3 「正しく生きる」とは何か――夢を追わせる社会・夢が追えない社会 4 今後の課題と展望 引用文献 初出一覧 おわりに 資 料 その1 研究参加者のプロフィール その2 職業分類の細目(第1章) 著者 野村 駿(ノムラ ハヤオ) 1992年岐阜県飛騨市生まれ.名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士課程満期退学.博士(教育学).秋田大学大学院理工学研究科附属クロスオーバー教育創成センター助教を経て,現在同大学教職課程・キャリア支援センター助教.専門は教育社会学,労働社会学. 主要論文に,「なぜ若者は夢を追い続けるのか――バンドマンの「将来の夢」をめぐる解釈実践とその論理」(『教育社会学研究』第103集),「不完全な職業達成過程と労働問題――バンドマンの音楽活動にみるネットワーク形成のパラドクス」(『労働社会学研究』20巻),「夢を諦める契機――標準的ライフコースから離反するバンドマンの経験に着目して」(『教育社会学研究』第110集). 著書に,『調査報告 学校の部活動と働き方改革――教師の意識と実態から考える』(共著,岩波ブックレット),『部活動の社会学――学校の文化・教師の働き方』(共著,岩波書店)など.本書が初の単著.
-

Book Arts and Crafts vol.8 本が届くまでの物語
¥1,100
SOLD OUT
本づくり学校の運営サポートを中心に、本づくりの技術と文化の普及・啓蒙につながるワークショップイベントを開催している「本づくり協会」が年1回発行する会報誌。 特集 本が届くまでの物語 インタビュー ビーナイス杉田龍彦 本と出会う”奇跡” ビーナイスの本 インタビュー 小説家 ほしおさなえ 本を問う 工場探訪 「活字の景色」活版印刷・嘉瑞工房を訪ねて(取材・文 永岡綾 写真・高見知香) 連載 上島松男物語 その4 故郷の名で、ひとり立つ(イラスト・望月通陽 書影・守屋史世 聞き手・上島明子 美篶堂代表 文・永岡綾) BOOK ARTS AND CRAFTS VOL.8 A5版 32ページ 並製・中綴じ 表紙の紙 みやぎぬ 色 たちばな 本文の紙 タブロ 栞の紙 NT ほそおりGA 色 ひまわり 2023年11月発行
-

製本と編集者 vol.2
¥1,320
SOLD OUT
これまでの出版業界にとって本を作るということは疑う余地もなく、紙の本を作るということだった。電子書籍が登場し、多くの人たちが当たり前にそれを読む端末を手にし、紙の本の価値を問われるようになって久しいが、それでもまだ紙の本のほうが商売になる(儲かる)という理由で、なんだかんだと紙の本は作られ続けている。けれど商売になるかどうか以前に、どうして紙の本をいいと思うのか説明できるようになりたい。それは自分がこの先もこの仕事を続けていく理由に繋がるはずだからだ。 製本の現場から、三人の編集者へ問いかける これからの本についてのインタビュー、シリーズ第二弾 編者:笠井瑠美子 話す人:松井祐輔(エイチアンドエスカンパニー (H.A.B))、三輪侑紀子(岩波書店)、藤枝大(書肆侃侃房) 松井祐輔 まつい・ゆうすけ 一九八四年、愛知県名古屋市生まれ、春日井市育ち。千葉大学文学部史学科卒。出版取次の株式会社太洋社に勤務の後、株式会社筑摩書房、NUMABOOKSを経て、現在は無所属。二〇一四年に『HAB』を刊行。以降は断続的に『ナンセンスな問い』(友田とん)、『山學ノオト』(青木真兵、青木海青子)、『台湾書店百年の物語』(台湾独立書店文化協会)、『パリと本屋さん』(パリュスあや子)などの書籍を刊行。二〇一四年から「小屋BOOKS」、二〇一五年には移転し「H.A.Bookstore」として実店舗を運営。二〇二〇年に閉店し、現在はwebのみで販売を行う。並行して取次業も担う。本を売って生きている。 三輪侑紀子 みわ・ゆきこ 一九八七年、静岡県浜松市生まれ。二〇一〇年頃から角川春樹事務所書籍編集部アルバイト。二〇一四年頃から編集部員に。二〇一九年岩波書店入社。所属は児童書編集部。二〇二〇年に出産。二〇二一年頃から『図書』編集部にも参加。二〇二三年の担当書は『地図と星座の少女』『ローラ・ディーンにふりまわされてる』『クロスオーバー』『モノクロの街の夜明けに』『ナイチンゲールが歌ってる』。 藤枝大 ふじえ・だい 一九八九年に八丈島で生まれ、関西で育つ。未知谷を経て、二〇一七年より書肆侃侃房で勤務。主に詩歌、海外文学、人文書、文芸誌の編集をしている。短歌ムック「ねむらない樹」 (編集統括)、文学ムック「ことばと」、「現代短歌クラシックス」シリーズのほか、『左川ちか全集』『葛原妙子歌集』『はじめまして現代川柳』『うたうおばけ』『月面文字翻刻一例』『象の旅』『赤の自伝』『路上の陽光』『ベルクソン思想の現在』などの編集を担当。海外文学と詩歌の書店「本のあるところ ajiro」を二〇一八年に立ち上げ、運営している。 ページ数 106 判型 A5判 装丁 千葉美穂(Ophelia Design Studio.) 著者プロフィール 笠井瑠美子(編著) 一九八〇年生まれ。横浜市育ち。武蔵野美術大学デザイン情報学科卒業後、株式会社東京印書館に入社。退職後、デザイン制作会社に勤務する傍ら、手製本工房まるみず組で手製本を習う。加藤製本株式会社で束見本担当、二〇一九年退職。二〇二〇年一月より、株式会社松岳社で引き 続き束見本を担当することになりました。束見本以外にもいろいろな作業をするのですが楽しいです。 行きつけは今野書店、時々Title。本を売る先は古本屋の音羽館。かもめブックスは第五の故郷です。 ・『本を贈る』(三輪舎)共著 ・『先生』(生活綴方出版部)寄稿 ・H.A.Bノ冊子「製本する人々」連載中 ・dee’s magazine コラム連載中
-

Je suis l? ここにいるよ
¥2,640
SOLD OUT
この世を去った愛猫が、悲しみにくれるボクに寄り添い語りかける――「ここにいるよ」。 愛しい姿、声、しぐさ、ぬくもり、匂い、よみがえる幸せな日の記憶。 大切な存在を失った悲しみを抱きしめ、涙を越えた愛と絆に気づかせてくれる感動の絵本。 透ける用紙をつかったしかけや箔押しカバーが美しく、ギフトにもおすすめです。 「そばにいてほしい、って もう寂しく思わないくらい、愛する存在と溶け合って自分の一部になる、 そんな日がきっとくる。」――――― 坂本美雨(ミュージシャン) 著者プロフィール シズカ (シズカ) (著/文 | イラスト) 2016年、『ココニイルヨ』の小さな絵本ダミーを携え、イタリア・ボローニャ・ブックフェアへ。2017年、ベルギーの出版社Alice Jeunesseより 『Je suis là 』で絵本作家デビュー。本作は原案『ココニイルヨ』に立ち返り、再構成した初の日本語版。近著に藤井カゼッタとの共著『ナイアル』(フレーベル館)がある。
-

よっちぼっち 家族四人の四つの人生
¥2,200
SOLD OUT
手話をことばとして生きる写真家・齋藤陽道さんの人気連載が一冊になりました。 齋藤さんは「聞こえる家族」に生まれたろう者、妻のまなみさんは「ろう家族」に生まれたろう者。そんなふたりの間には、聞こえる子どもがふたり――。 一家は、それぞれの違いを尊重しながら、手話で、表情で、体温で、互いの思いを伝え合います。 本書は、美しい写真とともに紡がれた育児記であり、手話でかかわり合うからこそもたらされた気づきと喜びの記録です。 著者について 齋藤陽道 1983年、東京都生まれ。写真家。都立石神井ろう学校卒業。2020年から熊本県在住。陽ノ道として障害者プロレス団体「ドッグレッグス」所属。2010年、写真新世紀優秀賞受賞。2013年、ワタリウム美術館にて新鋭写真家として異例の大型個展を開催。2014年、日本写真協会新人賞受賞。写真集に『感動』、続編の『感動、』(赤々舎)で木村伊兵衛写真賞最終候補。著書に『異なり記念日』(医学書院・シリーズ ケアをひらく、第73回毎日出版文化賞企画部門受賞)、『声めぐり』(晶文社)など。 2022年には『育児まんが日記 せかいはことば』(ナナロク社)を発行。同年、Eテレ『おかあさんといっしょ』のエンディング曲『きんらきら ぽん』の作詞を担当。写真家、文筆家としてだけでなく、活動の幅を広げている。 Kindle→https://amzn.to/47MmEC9
-

色の物語 青
¥3,300
SOLD OUT
青について深く知りたい人に。青の歴史をたどる旅 ◆巨匠たちが好んだ青の秘密 葛飾北斎の好んだ青の秘密。ゴッホが神の色とあがめたコバルトブルー。ピカソによる美しくも陰鬱な青。モネの青い睡蓮は、多くの作家に影響を与えました。 美術史において、青という色の影響力は計り知れません。本書では、青を用いた著名な美術作品のビジュアルを多数掲載、青色と美術作品の切っても切れない関係を、気鋭のフランス人美術史研究家が解説します。 ◆青の成り立ちと歴史を知る ラピスラズリのような鉱石、インディゴやパステルといった植物による青など、さまざまな青色の由来について紹介。 主要な青色色素のルーツを世界地図上で俯瞰できるほか、天然色素や合成色素からどのように絵の具として使える色になっていったのかまで、図解でわかりやすく紹介しています。 ◆構成(抜粋) アートの中の青/青の世界地図/青のバリエーション/アメンホテプ3世のスフィンクス/手紙を読む青衣の女(フェルメール)/神奈川沖浪裏(葛飾北斎)/星月夜(ゴッホ)/大水浴図(セザンヌ)/自画像(ピカソ)/青い睡蓮(モネ)/青い裸婦 III(マティス)/とても大きな水しぶき(ホックニー)/空の青(カンディンスキー)ほか ◆「色の物語」シリーズ その色はどこから来て、どこへ向かうのか。古今東西文明のなかで、さまざまな意図で使われてきた「色」の歴史とストーリー、影響力を、名だたるアート作品の美しいビジュアルでたどる。地図や図解、年表等のグラフィックも豊富に盛り込み、多彩な角度からの解説が特徴。本書はその第一弾。続編として「ピンク」「黒」「赤」「ゴールド」刊行予定。 【著者について】 ヘイリー・エドワーズ=デュジャルダン 美術史・モード史研究家。エコール・デュ・ルーヴル、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション卒業。キュレーター、フリーランスのライターとして、ヴィクトリア・アンド・アルヴァート美術館の調査事業や展覧会に協力するほか、個人コレクター向けのコンサルタントとしても活躍する。ギ・ラロッシュのメゾンのアーカイブ部門の設立を手がけた。パリでモード史、ファッション理論の教鞭をとる。 【翻訳者について】 丸山有美 Ami MARUYAMA フランス語翻訳者・編集者。フランスで日本語講師を経験後、日本で芸術家秘書、シナリオライターや日仏2か国語podcastの制作・出演などを経て、2008年から2016年までフランス語学習とフランス語圏文化に関する唯一の月刊誌「ふらんす」(白水社)の編集長。2016年よりフリーランス。ローカライズやブランディングまで含めた各種フランス語文書の翻訳、インタビュー、イベント企画、イラスト制作などを行なう。 Kindle→https://amzn.to/3QULyZB
-
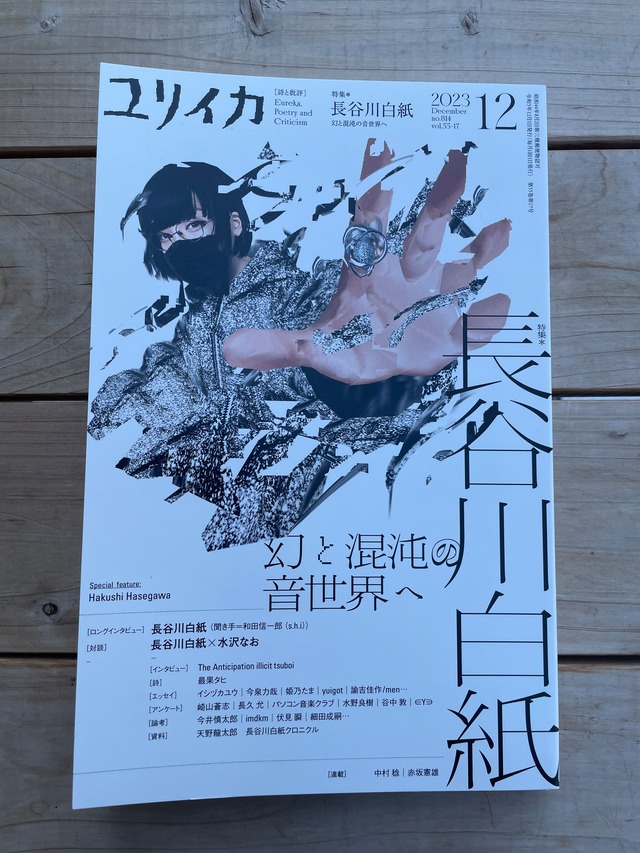
ユリイカ2023年12月号 特集=長谷川白紙
¥1,980
SOLD OUT
加速し攪乱するシンガーソングライター 多種多様な音楽のエッセンス、柔らかな肉声、不可思議なことばの連なり、それらをデスクトップ上で混ぜ合わせた唯一無二の「歌」を、衝撃と混乱とともに轟かせてきた長谷川白紙。LAを拠点とするBrainfeederとの契約が発表され、ますます世界中で注目度を高める革新的なサウンドに身を委ねれば、これからの音楽が聴こえてくる。「わたし自身の身体による音楽の攪乱」――長谷川白紙自身によるマニフェストを受け取り、CDデビュー5周年を迎えた先にひろがるカオスな風景を描き出す。 line2.gif 特集*長谷川白紙──混沌の音世界へ ❖対談 からだの言葉、言葉のからだ / 長谷川白紙×水沢なお ❖詩 新しい恋 / 最果タヒ ❖長谷川白紙と邂逅する 好き長谷川白紙 / 諭吉佳作/men いつくしい日々の思い出 / 姫乃たま 長谷川白紙とスペクトル / 今井慎太郎 ❖わたしたち、一緒にいたっぽい 複雑な音楽性が自由なノリを生む――長谷川白紙のライブにおける「権威性に対する撹乱」、付かず離れずの軽やかな連帯感 / 和田信一郎(s.h.i) ハクシトワタクシ / タカノシンヤ 始まりの季節 / スッパマイクロパンチョップ ❖インタビュー 変容し続ける音楽と肖像 / 長谷川白紙 聞き手=和田信一郎(s.h.i) ❖音から想像を広げて 音の光 / 海野林太郎 さまよう映像制作 / 松永昂史 草木萌え尽きぬ / イシヅカユウ ❖オマージュイメージギャラリー 『草木萌動』(二〇一八) / 相磯桃花 『エアにに』(二〇一九)「ユニ」(二〇二一) / 浦川大志 / from_photobooth 『夢の骨が襲いかかる!』(二〇二〇) / KOURYOU 『音がする』(二〇二〇)『巣食いのて』(二〇二一) / しばしん+竹久直樹+米澤柊 『アイフォーン・シックス・プラス』(二〇一七) / 山形一生 ❖長谷川白紙を媒介するもの コンテンポラリー・アートの場としての長谷川白紙と過剰な装飾――アヴァンギャルドでキッチュ / きりとりめでる 長谷川白紙と多受肉するペルソナたち――声と身体をめぐる新たな表現ジャンル「多受肉する歌い手」の誕生――ARuFa、月ノ美兎、ヨルシカ、ずっと真夜中でいいのに。、Ado、いよわ――について / 難波優輝 ❖アンケート 長谷川白紙さんへ / 水野良樹・崎山蒼志・∈Y∋・谷中敦・長久允・パソコン音楽クラブ ❖居心地の良いカオス 『エアにに』 言葉のオブジェクティビティ――テクスチャの豹と歌詞空間の庭を作る / 青島もうじき 無性のエコー / 原島大輔 破断と攪乱――長谷川白紙の詞におけるクィアネス / 青本柚紀 ❖音楽と音楽を繋ぐ 混乱し続ける音楽と僕たち / The Anticipation illicit tsuboi 聞き手=編集部 新たな混乱――長谷川白紙とBrainfeederについて / 坂本哲哉 ジャズとして語られる『草木萌動』 / 細田成嗣 混沌と速度、落差と歌――長谷川白紙といくつかのボカロ曲について / Flat 音がする / yuigot 長谷川白紙さんについて / 今泉力哉 ❖長谷川白紙の聴き方 混沌、断絶、グルーヴ――長谷川白紙のリズムの実践を観察する / imdkm 『アイフォーン・シックス・プラス』についてのメモ / 灰街令 からだのきらいなわたしのからだ――『夢の骨が襲いかかる!』から聴き取る、「編まれ直し」としてのクィア・ファンク / 伏見瞬 ❖資料 長谷川白紙クロニクル / 天野龍太郎 ❖忘れられぬ人々*26 故旧哀傷・副島有年 / 中村稔 ❖物語を食べる*34 異端の鳥たちが空を舞う / 赤坂憲雄 ❖詩 Eyeless in Gaza / 四方田犬彦 ❖今月の作品 朱泪みね・山内優花・のもとしゅうへい・木下多尾・栫伸太郎・赤澤玉奈 / 選=大崎清夏 ❖われ発見せり 人形愛者の秘かな愉しみ / 谷口奈々恵 表紙・目次・扉……北岡誠吾 扉イラスト……相磯桃香
-

その世とこの世
¥1,760
SOLD OUT
いまここの向こうの「その世」に目を凝らす詩人と、「この世」の地べたから世界を見つめるライターが、1年半にわたり詩と手紙を交わした。東京とブライトン、老いや介護、各々の暮らしを背景に、言葉のほとりで文字を探る。奥村門土(モンドくん)描きおろしイラストを加えての、三世代異種表現コラボレーション。 目次 邪気の「あるとない」………ブレイディみかこ 萎れた花束………谷川俊太郎 Flowers in the Dustbin………ブレイディみかこ その世………谷川俊太郎 青空………ブレイディみかこ 座標………谷川俊太郎 詩とビスケット………ブレイディみかこ 現場………谷川俊太郎 淫らな未来………ブレイディみかこ 気楽な現場………谷川俊太郎 秋には幽霊がよく似合う………ブレイディみかこ 幽霊とお化け………谷川俊太郎 ダンスも孤独もない世界………ブレイディみかこ 父母の書棚から………谷川俊太郎 謎の散りばめ方………ブレイディみかこ 笑いと臍の緒………谷川俊太郎 ウィーンと奈良………ブレイディみかこ Brief Encounter………谷川俊太郎 Kindle→https://amzn.to/47smuQH
-

音楽(ビート)ライター下村誠アンソロジー 永遠の無垢
¥2,750
SOLD OUT
1970年代~1990年代の日本の音楽シーンは音楽雑誌も熱かった! かつて下村誠という音楽ライターがいた。活動していたのは、主に1970年代後半から90年代。『シンプジャーナル』など音楽雑誌を中心に、ミュージシャンの想いや活動、魅力を伝えた。音楽ライターであると同時にミュージシャンでもあった彼は自らのインディーズレーベルを設立し、音楽をつくり、若いミュージシャンも発掘して、育てた。1970年代~90年代というと、ちょうど、日本人の生活スタイルや価値観が大きく変わってきた時期。そんな時代を切り開き、自由で多様な音楽シーンを拓いてきたミュージシャンたちの若き日の言葉を、下村誠が遺した音楽雑誌の記事を通して伝えるアンソロジー。 【目次】 第一章 音楽(ビート)ライター下村誠の仕事1 アルフィー/伊藤銀次/エコーズ/大塚まさじ/吉川晃司/佐藤奈々子 第二章 時代と音楽シーン 第三章 音楽(ビート)ライター下村誠の仕事2 ザ・ストリート・スライダーズ/ザ・ストリート・ビーツ/ザ・ブルーハーツ/篠原太郎/シバ/白鳥英美子/ジュンスカイウォーカーズ/高田渡/友部正人/中川イサト/西岡恭蔵/浜田省吾/ふきのとう/真島昌利 第四章 アーティストからの言葉(インタビュー) 西本明 スズキコージ 第五章 仲間たちからの言葉 付録 下村誠の詩(うた)/1954~2006 下村誠と彼が生きた時代の音楽シーンと世相年表 特別寄稿 田家秀樹 山本智志 中川五郎
-

ベートーヴェン捏造 文庫
¥990
SOLD OUT
音楽史上最大のスキャンダル「会話帳改竄事件」。宮部みゆき氏絶賛の衝撃的歴史ノンフィクション!、待望の文庫化! 現代に語り継がれるベートーヴェン像は、秘書により捏造されていた!? 「会話帳改竄事件」の真相に迫る、衝撃的な歴史ノンフィクション。「会話帳」とは、聴力を失ったベートーヴェンが周囲の人とコミュニケーションを取るために用いた筆談用ノートのこと。 100年以上にもわたり多くの人々を騙し続けた「犯人」の名は、アントン・フェリックス・シンドラー。音楽家でもあり、誰よりもベートーヴェンの近くで忠誠を誓い、尽くした人物である。なぜ、何のために彼は改竄に手を染めたのか? 音楽史上最大のスキャンダルの「犯人」・シンドラーの目を通して、19世紀の音楽業界を辿る。音楽ファンもミステリーファンも絶賛した名作がついに文庫化! ◎解説=栗原康 目次 序曲 発覚 第一幕 現実 第一場 世界のどこにでもある片田舎 第二場 会議は踊る、されど捕まる 第三場 虫けらはフロイデを歌えるか 第四場 盗人疑惑をかけられて 第五場 鳴りやまぬ喝采 間奏曲 そして本当に盗人になった バックステージⅠ二百年前のSNS──会話帳からみえる日常生活── 第二幕 噓 第一場 騙かたるに堕ちる 第二場 プロデューサーズ・バトル 第三場 噓vs噓の抗争 第四場 最後の刺客 バックステージⅡメイキング・オブ・『ベートーヴェン捏造』──現実と噓のオセロ・ゲーム── 終曲 未来 単行本版 あとがき 文庫版 あとがき 解説 栗原康 関連年表 註 著者 かげはら 史帆 (カゲハラ シホ) 1982年、東京郊外生まれ。法政大学文学部日本文学科卒業、一橋大学大学院言語社会研究科修士課程修了。著書に『ベートーヴェンの愛弟子 』、『ニジンスキーは銀橋で踊らない』がある。 Kindle→https://amzn.to/3SvHMsb
-

パピルスのなかの永遠 書物の歴史の物語
¥5,280
SOLD OUT
世界100万部の大ベストセラー スペインでもっとも著名な作家のひとりである著者が贈る、書物の歴史のはじまりを綴った、壮大な一冊。 「今日の読者が来世にあるときもなお、この本は読み継がれゆくだろうという、絶対的な確信がある」――マリオ・バルガス=リョサ 「書物の発明は破壊に対する私たちの粘り強い戦いにおける、最大の偉業かもしれない」(本書より) 約三千年以上にわたる書物の歴史の黎明期にスポットを当て、口承から、巻物、冊子本(コデックス)に至るまでの書物とそれを受け継いできた人々の足跡、図書館の誕生やアルファベットによる革命、読書、書店など、本にまつわる事象をたどる。アリストパネスと喜劇作家に対する司法手続き、サッポーと文学における女性の声、ティトゥス・リウィウスとファン現象、セネカとポスト真実など、現代の社会現象や文学作品、映画にも言及しながら、エッセイの形式で書物の激動の旅が描かれる世界的ベストセラー。 本をつくり、受け継ぎ、守るために戦う――。 目次 プロローグ 第一部 未来に思いを馳せるギリシア 快楽と書物の都市 アレクサンドロス―あきたらぬ世界 マケドニアの友 深淵の縁の均衡――アレクサンドリアの大図書館とムセイオン 炎と暗渠の物語 書物の皮膚 探偵の任務 ホメロス、それは謎と衰退 失われた声の世界――こだまする音のタペストリー アルファベットの穏やかな革命 雲間からとどく声、定まらぬ空もよう 影の読み方を学ぶこと 反抗的な言葉の勝利 最初の書物 移動書店 文化という信仰 驚くべき記憶力の男と前衛派の女性グループ 物語の織り子たち 私の物語を語るのは他者 笑いのドラマとゴミ捨て場の恩恵 言葉との情熱的な関係 書物の毒。書物の儚さ アレクサンドリアの大図書館の三度の崩壊 救命ボートと黒い蝶 こうして私たちはこれほど奇妙ないきものとなった 第二部 ローマの街道 悪名高い都市 敗北の文学 奴隷化の見えない境界線 最初は木だった 貧しい著者、裕福な読者 うら若い一族 書店員――危険な仕事 ページのある書物の揺籃期と成功 湯の宮殿の公共図書館 二人のスペイン人――最初の熱狂者(ファン)と最初の熟練作家 ヘルクラネウム――破壊による保存 検閲と戦うオウィディウス 甘い惰性 書物の内側への旅路と名づけかた 古典(クラシック)とはなにか 正典(カノン)――水生植物の物語 女性の声の断片 永遠のものと信じられていたものは儚かった あえて記憶にとどめること エピローグ――忘れ去られた者たち、名もない者たち 謝辞 訳者あとがき 参考文献 註 索引 著者プロフィール イレネ・バジェホ (イレネ バジェホ) (著/文) (Irene Vallejo)1979年、スペインのアラゴン州サラゴサに生まれる。サラゴサ大学とフィレンツェ大学で古典文献学の博士号を取得。『エル・パイス』紙や『エラルド・デ・アラゴン』紙などでコラムを担当。小説、児童書、コラム集も出版されている。『パピルスのなかの永遠』(2019)は、世界100万部の大ベストセラーとなっている。本屋大賞ノンフィクション部門(2020)、国内最高峰の文学賞であるスペインエッセイ賞(2020)ほか多数を受賞。 見田 悠子 (ミタ ユウコ) (翻訳) (みた・ゆうこ)ラテンアメリカ文学研究者、大学講師。専門はガルシア=マルケス。論文・論考に、「黄金郷の孤独」(『れにくさ』現代文芸論研究室、2013)、「いくつもの世界のひしめく文学」(『ユリイカ』青土社、2014)、「『眠れる森の美女』以降のガルシア゠マルケス」(『〈転生〉する川端康成』文学通信、2022)ほか。訳書に、ジョシュ『バイクとユニコーン』(東宣出版)、サマンタ・シュウェブリン『七つのからっぽな家』(河出書房新社)ほかがある。